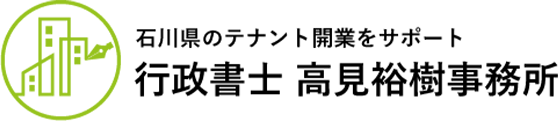“家族がもめないために”
公正証書遺言の作成と行政書士の関わり
【遺言 × 公正証書】
はじめに
「子どもたちが相続で揉めないようにしたい」
「自分が元気なうちに財産の分け方をはっきり決めておきたい」
──そんな思いから「遺言」を考える方が増えています。
しかし、せっかく遺言書を作っても、
書き方の誤りや法的効力の欠落によって「無効」になってしまうケースも少なくありません。
その中で最も安全で確実な方法が「公正証書遺言」です。
この記事では、公正証書遺言の仕組み・作成の流れ・費用の目安、
そして行政書士がどのように関わるのかを、実務経験に基づいてわかりやすく解説します。
1.公正証書遺言とは?
遺言にはいくつかの形式がありますが、代表的なものは次の3種類です。
| 遺言の種類 | 作成方法 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で全文・日付・署名押印を記す | 費用がかからないが、形式不備・紛失リスクあり |
| 公正証書遺言 | 公証人が内容を確認し、公証役場で作成 | 法的効力が確実で、原本が公証役場に保管される |
| 秘密証書遺言 | 内容は秘密のまま、公証役場で封印 | 実務上はほとんど使われない |
この中で最も確実で、後の相続トラブルを防げるのが「公正証書遺言」です。
なぜなら、公証人が本人の意思を直接確認し、法律に沿った形式で作成するため、
「無効になる心配がほとんどない」からです。
2.なぜ公正証書遺言が選ばれるのか
① 紛失・改ざんの心配がない
原本は公証役場に保管され、全国の「公証人連合会システム」で照会可能。
万が一、家族が遺言書を見つけられなくても、存在を確認できます。
② 家庭裁判所の検認が不要
自筆証書遺言とは違い、家庭裁判所での「検認手続き」を経る必要がありません。
相続発生後、すぐに遺言の内容を実行できます。
③ 内容の不備を防げる
公証人が法律的にチェックして作成するため、
「書き方の間違い」「署名漏れ」「押印忘れ」などの形式ミスが起こりません。
3.作成までの流れ
公正証書遺言の作成は、主に次のステップで進みます。
STEP1.行政書士との事前相談・内容整理
まず、行政書士がご本人の希望をヒアリングし、
財産の内容・相続人構成・希望する分け方などを整理します。
この段階で作るのが「遺言原案(下書き)」です。
「誰に」「どの財産を」「どんな理由で」渡すかを明確にしておきます。
※この時点で、戸籍謄本や固定資産評価証明書などを収集します。
STEP2.公証人との事前打合せ
行政書士が作成した原案をもとに、公証人と文案調整を行います。
内容の法的確認や文言修正、必要資料の確認などをこの時点で済ませます。
公証人から「証人2名の立会いが必要」と指示があり、
当事務所では、必要に応じて証人を手配することも可能です。
STEP3.公証役場での作成
予約した日時に公証役場へ出向きます。
公証人が本人の意思を口頭で確認し、遺言内容を読み上げます。
本人が署名・押印し、証人2名も立ち会って署名します。
これで公正証書遺言が正式に成立します。
STEP4.原本保管・正本交付
遺言書の原本は公証役場に保管され、本人には「正本」「謄本」が交付されます。
原本が紛失しても再発行可能なため、長期的に安心です。
4.公正証書遺言の費用目安
公証役場でかかる手数料は、財産額によって異なります。
| 財産の総額 | 公証人手数料(目安) |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 約1万1,000円 |
| 3,000万円以下 | 約2万3,000円 |
| 5,000万円以下 | 約2万9,000円 |
| 1億円以下 | 約4万3,000円 |
| それ以上 | 別途加算あり |
このほか、行政書士による原案作成・資料収集・証人立会い等のサポート費用が発生します。
一般的な目安として、総額5万〜10万円前後(実費込み)が多いです。
5.証人の要件と注意点
公正証書遺言では、証人2名の立会いが必須です。
ただし、次の人は証人になれません。
- 相続人およびその配偶者・直系血族
- 未成年者
- 公証人の職員
証人の署名押印が欠けると遺言自体が無効になるため、
専門家が立ち会うのが安心です。
当事務所では、行政書士と職員が証人として立ち会うケースが多く、
ご家族に余計な気遣いをさせないよう配慮しています。
6.よくある質問
Q1. 公証役場へ行けない場合はどうすればいいですか?
→ 公証人が出張してくれる制度があります(病院・介護施設など)。
出張費・日当が加算されますが、自宅でも作成可能です。
Q2. 一度作った遺言は変更できますか?
→ 可能です。後日、新しい公正証書遺言を作成すれば、前の内容は自動的に無効になります。
Q3. 相続人以外の人にも財産を渡せますか?
→ できます。ただし税務上の扱いが異なるため、税理士との連携が望ましいです。
Q4. 行政書士と司法書士の違いは?
→ 行政書士は内容作成・文案整理・証人立会いが可能です。
登記が必要な場合は、提携司法書士が対応します。
7.行政書士が関わるメリット
公正証書遺言の作成は、公証人とのやり取りや資料準備が意外と煩雑です。
行政書士がサポートに入ることで、次のような利点があります。
- ご本人の意向を丁寧にヒアリングし、わかりやすく文章化できる
- 戸籍・評価証明書などの書類収集を代行できる
- 公証人との打合せや日程調整を一括で任せられる
- 証人の手配・当日立会いまで対応できる
特に、初めて公証役場へ行く方にとって、
「何を持っていけばいいか」「何を話せばいいか」が明確になるため、心理的な負担が大きく減ります。
8.作成時の注意点
- 「相続人の順位」や「法定相続分」を無視するとトラブルの原因になります。
- 財産の表現(例:○○銀行○○支店の預金口座)は具体的に。
- 不動産は登記簿記載の「所在地・地番・家屋番号」を正確に記載。
- 「付言事項」を活用して、家族への想いを言葉で残すのも有効です。
行政書士は、こうした「法律+気持ち」のバランスを取る文章化が得意です。
9.実際のケース
事例①:金沢市在住・80代男性のケース
相続人:長男・長女・次男
→ 自筆証書遺言の文面を整理し、公証役場用に原案化。
行政書士が証人手配・日程調整まで対応。作成当日も同席。
事例②:白山市在住・70代女性のケース
→ 不動産が複数あり、財産目録を行政書士が整理。
内容を法定相続分に沿って調整し、公証人とスムーズに連携。
事例③:施設入居中の女性のケース
→ 公証人が病院に出張。行政書士が本人確認と立会いを補助。
意思確認の記録を残すことで、後日の争いを回避。
10.まとめ
公正証書遺言は、「家族がもめないための最善の準備」です。
専門家が関与することで、形式ミスや手続き漏れを防ぎ、
安心して想いを形にすることができます。
行政書士高見裕樹事務所では、
・遺言内容のヒアリングと原案作成
・公証人との文案調整
・証人手配・立会い
・戸籍や財産資料の収集
をトータルでサポートしています。
【お問い合わせ】
行政書士高見裕樹事務所
TEL:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/