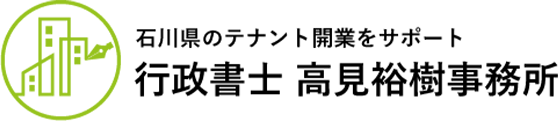融資・補助金を味方に!|事業計画書づくりから始める開業準備
1. はじめに
「開業のために資金をどうするか?」
多くの方が最初に直面する課題は、やはりお金の確保です。
自己資金だけで事業をスタートできれば理想ですが、実際には店舗取得費、内装工事費、設備購入費、運転資金など、多額の費用が必要です。
そこで頼りになるのが 日本政策金融公庫や信用金庫からの融資、そして国や自治体の補助金制度です。
ただし、融資や補助金を受けるためには「事業計画書」が欠かせません。しかも単なる作文ではなく、数字の根拠を持った計画書が求められます。
この記事では、石川県で多数の開業支援を行ってきた行政書士高見裕樹事務所の実務経験をもとに、事業計画書の作り方と、その活用法を徹底解説します。
2. 事業計画書とは何か?
事業計画書とは、簡単に言えば「これからどんな事業を始め、どうやって利益を出していくか」をまとめた書類です。
銀行や公庫に対しては「返済能力を示す資料」、補助金の審査に対しては「事業の実現性を証明する資料」として機能します。
2-1. 主な構成要素
- 事業の目的・背景
- 提供する商品・サービスの特徴
- 市場分析・競合状況
- 立地条件・ターゲット顧客
- 売上計画・利益計画
- 必要な資金と資金調達方法
- 事業の将来展望
これらをバランスよく記載することが重要です。
3. 融資審査で重視されるポイント
3-1. 日本政策金融公庫の場合
- 自己資金の割合
→ 全体の1/3以上を自己資金で用意していると評価が高い。 - 経験・実績
→ 飲食店を開業するなら、飲食業での勤務経験が必須レベル。 - 収支計画の現実性
→ 「初年度から黒字」と書いても、根拠がなければ信用されない。
3-2. 信用金庫・地方銀行の場合
- 地域性を重視
→ 立地条件、商圏人口、競合の有無が審査に大きく影響。 - 事業主の人物像
→ 面談での説明力、誠実さも重要視される。 - 返済計画の具体性
→ 借入金の返済を「売上」からどう確保するか、具体的に問われる。
4. 補助金申請で評価されるポイント
4-1. 代表的な補助金制度
- 小規模事業者持続化補助金
- 事業再構築補助金
- IT導入補助金
4-2. 補助金が重視する視点
- 新規性・独自性
→ 単なる模倣ではなく、地域に新しい価値を提供するか。 - 成長性
→ 数字で成長の根拠を示せるか。 - 地域貢献性
→ 地元雇用や地域活性化につながるか。
5. 数字に強い行政書士が作る事業計画書
行政書士高見裕樹事務所では「数字に強い」という強みを活かし、以下のサポートを行っています。
- 現実的な売上予測
- 客単価 × 回転率 × 営業日数で算出
- 根拠をデータで裏付け
- 資金繰り計画の作成
- 融資返済額を組み込み、資金ショートを回避
- 初期費用・運転資金を分けて試算
- 複数シナリオの提示
- 楽観シナリオ・標準シナリオ・悲観シナリオを作り、リスク管理を明示
- 許認可申請との連動
- 風俗営業や旅館業許可では「事業計画書」が審査資料として利用できるケースもあり、一度の作成で二重の効果がある。
6. 計画書を許認可申請にも活用できるメリット
事業計画書は融資や補助金だけでなく、許認可申請の補強資料としても活用可能です。
- 飲食店営業許可 → 衛生管理計画とリンク
- 旅館業許可 → 収容人数や運営体制の裏付けに活用
- 風俗営業許可 → 営業の健全性を示す資料に活用
つまり「一度作って終わり」ではなく、複数の手続きで役立つ万能資料になるのです。
7. 実例紹介
7-1. 飲食店開業の例
金沢市で居酒屋を開業したいという依頼者。
- 自己資金200万円
- 公庫に600万円を申請
- 客単価3,000円、席数30、回転率1.5回で売上計画を作成
→ 融資がスムーズに下り、予定通り開業。
7-2. 簡易宿所開業の例
古民家をリノベーションして宿泊業を始めたいという相談。
- 改装費用に補助金を活用
- 事業計画書で「地域観光資源との連携」をアピール
→ 持続化補助金に採択され、資金負担を軽減して開業。
8. まとめ
- 融資・補助金を受けるには事業計画書が必須。
- 数字の根拠を示し、現実的で説得力ある計画が求められる。
- 行政書士高見裕樹事務所は「数字に強い」ことを活かし、計画書づくりから許認可申請までワンストップで支援。
開業を成功させるためには、最初に事業計画書を作ることが何よりの近道です。
✅ お問い合わせ先
行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/