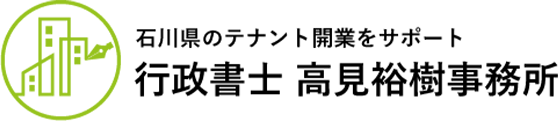任意後見契約とは?|認知症や将来の不安に備える生前対策
はじめに
「将来、認知症になったら財産管理はどうするの?」
「子どもに迷惑をかけたくないけど、自分で判断できなくなったら不安…」
こうしたお悩みに備える制度が 任意後見契約 です。
元気なうちに信頼できる人へ財産管理を任せる準備をしておくことで、本人も家族も安心できます。
任意後見契約とは?
- 本人が元気なうちに「将来、判断能力が低下したときに代理してほしい内容」を契約で決めておく制度
- 公正証書で作成 → 家庭裁判所で後見監督人が選任されて発効
- 財産管理や生活支援を「誰に・どこまで」任せるかを自由に設定できる
👉 法律に基づいた契約なので、親族間のトラブル防止にも有効です。
法定後見との違い
| 項目 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 判断能力が低下した後、契約内容に基づき開始 | 判断能力が低下してから家庭裁判所が開始 |
| 本人の意思 | 本人が元気なうちに契約で決定 | 本人の意思反映が難しい場合も多い |
| 内容 | 財産管理・身上監護の範囲を自由に決定可 | 裁判所が後見人の権限を決定 |
| 後見人 | 本人が選んだ信頼できる人 | 裁判所が選任(専門職が就く場合あり) |
👉 「自分で決めておきたい」なら任意後見、「すでに判断能力が低下している」なら法定後見 という住み分けになります。
任意後見契約でできること
- 預金通帳・出納の管理
- 年金・保険の受領
- 不動産の管理・売却(範囲を定めれば可能)
- 施設入所契約、医療費の支払い
- 日常生活費の支払い
※「身上監護」と「財産管理」の範囲を契約で具体的に設定できます。
任意後見契約の流れ
- 契約内容を決定
どこまで任せるか(財産管理・身上監護)を決める - 任意後見契約書の作成(行政書士が原案作成)
- 公証役場で公正証書により契約締結
- 発効は将来:本人の判断能力が低下し、家庭裁判所に監督人が選任された時点で開始
👉 契約してもすぐ効力は発生せず、**“将来の備え”**として機能します。
費用の目安
- 公証役場の手数料:約1〜2万円程度(契約内容により変動)
- 行政書士報酬:数万円〜(契約内容の設計・原案作成を含む)
- 裁判所が後見監督人を選任する際の費用:**月数万円(報酬)**が発生するケースあり
👉 契約時の費用よりも、「監督人の報酬」など長期的コストを見据えることが大切です。
実務での注意点
- 契約範囲を広げすぎない
不必要に制限されるリスクがあるため、必要な範囲に絞る - 信頼できる人を選任
任せる相手は家族だけでなく、第三者(行政書士など)も可 - 発効は家庭裁判所が関与
契約だけでなく、発効時には裁判所のチェックが入るため安心
行政書士に依頼するメリット
- 契約内容をヒアリングし、個別事情に合わせた原案を設計
- 公証役場との調整・必要書類の整備を代行
- 他士業(弁護士・司法書士・税理士)と連携し、資産内容や相続全体を見据えた設計が可能
- 将来の相続・不動産売却・事業承継と組み合わせたトータル対策
まとめ
任意後見契約は、**「将来に備えて自分で決めておく」**ための制度です。
- 認知症リスクに備え、信頼できる人に財産管理を任せられる
- 契約範囲を自由に設計でき、裁判所監督付きで安心
- 公正証書による確実な契約で、家族の負担を軽減
👉 石川県で任意後見契約を検討中の方は、行政書士高見裕樹事務所へお気軽にご相談ください。
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/