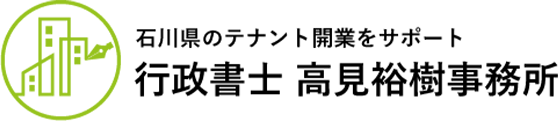相続不動産を早く売るなら「残置物処理」を正しく|所有権・同意・処分方法を実務解説
はじめに
相続直後は、相続人調査・相続登記・各種名義変更に加えて、家財や生活用品などの残置物が大きなハードルになります。
処理の仕方を誤ると、相続人間のトラブル化や違法処分(不用品回収業者の無許可行為等)、売却スケジュールの遅延につながります。
本記事では、相続不動産の売却と残置物処理を同時並行で進めるための実務ポイントを整理します。
残置物の“所有権”は誰にある?
- 相続開始時点で、被相続人の動産(家財・家電・衣類など)は相続人の共有財産になります。
- よって、処分・売却・寄付等には相続人全員の合意が原則必要です。
- 誰か一人の判断で処分すると、後日、費用負担・残置物の評価を巡る争いの種に。
👉 先に「相続人調査・相続関係説明図・法定相続情報」で相続人を確定し、合意形成の土台を整えるのが第一歩。
違法処分を避けるための基礎知識
- 家庭系残置物の大半は“一般廃棄物”に該当:収集運搬は市町村許可の一般廃棄物業者が原則。
- 産業廃棄物許可=家庭系ごみを運べるではありません(用途により許認可が異なります)。
- 家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)は家電リサイクル法に従い処分。
- 消火器・ガスボンベ・塗料など危険物は専用ルートへ。
- 古物商が関わる買取・再利用は適法に(台帳・本人確認等)。
👉 行政書士が適法な許可業者の手配と書面整備を行うことで、トラブルと違法リスクを回避できます。
見積りがブレる“3大要因”
- 体積(m³)と搬出動線:階段・エレベーター・駐車距離で大きく変動
- 仕分け難易度:貴重品探索・アルバム/位牌/書類の選別有無
- 特殊品の割合:家電4品目、金庫、ピアノ、危険物、庭石・外構残置 など
まずは現地確認 → 写真共有 → 概算提示 → 書面確定の順で進めるのが安全です。
よくある質問(FAQ)
Q. 先に残置物を全部捨ててから合意を取っても良い?
A. 原則NG。共有財産の処分は全員合意が前提です。まずは書面化を。
Q. 相続人の一人が連絡不通。作業は止めるべき?
A. 原則は停止して協議。状況により家庭裁判所の手続(不在者財産管理人等)を検討。
Q. 買取と廃棄はどちらが得?
A. 並行が基本。買取対象を先に“抜く”→残りを適法廃棄で総コスト最適化。
Q. 遠方在住で立会いできない。
A. 鍵の預かり・写真/動画報告・郵送での書面合意により非対面で完結可能です。
行政書士高見裕樹事務所のワンストップ
- 相続人調査 → 合意書作成 → 法定相続情報まで行政書士が主導
- 司法書士と連携して相続登記をスムーズに
- ふちどり不動産が買取・仲介を柔軟提案(現況売却も可)
- Kプランニングが搬出・簡易原状回復を迅速対応
- 許可業者ネットワークで、一般廃棄物・家電リサイクル・危険物まで適法処理
「やっかい・面倒」な案件ほどお任せください。最短で**“鍵と同意書”**から動きます。
まとめ
- 残置物は“相続人の共有” → まず合意と書面化
- 処分は許可業者で適法に(一般廃棄物/家電リサイクル等)
- 売却戦略は「現況売却」か「空室化」の二択を早期に決断
- 行政書士+司法書士+不動産+工事のワンストップが最短ルート
👉 相続不動産の売却と残置物処理のご相談は、行政書士高見裕樹事務所へ。
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/