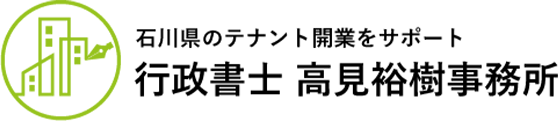【酒類販売免許を取得したい方へ】
“お酒を売るには免許が必要”|一般販売・通信販売の違いと取得のポイントを行政書士が解説します
はじめに|お酒を売るのに免許が必要なのはなぜ?
「飲食店をやっているけど、瓶ビールの持ち帰り販売もしたい」
「ネットショップで地酒の販売を始めたい」
「クラフトビールの製造者として、自社で販売もしたい」
こういった“お酒の販売”を考えたとき、必ず必要になるのが酒類販売業免許です。
「仕入れて売るだけなのに、なぜ免許が必要?」と思われるかもしれませんが、酒類は国税庁の管轄である“酒税”の対象商品であり、非常に厳格な制度設計がされています。
無免許で販売した場合は、**1年以下の懲役または50万円以下の罰金(酒税法違反)**という重い罰則も定められており、「知らなかった」では済まされません。
酒類販売免許の種類と、どれが必要かの判断基準
酒類販売免許にはいくつかの種類がありますが、まずは大きく分けて以下の2つがあります。
1. 一般酒類小売業免許(店舗で対面販売)
- 店舗で不特定多数の顧客に酒類を販売するための免許
- コンビニ・酒屋・飲食店での「持ち帰り販売」などに該当
- 実店舗があり、顧客が来店して購入する形式
2. 通信販売酒類小売業免許(ネット通販など)
- ECサイトや電話・FAXなど「非対面」で酒類を販売するための免許
- 全国配送・海外発送も視野に入れたビジネスに対応
- 地方の酒蔵や飲食店が、地酒や自社ブランド商品をオンライン販売したい場合に必要
※このほかにも、「輸出入用」や「卸売用」などの特殊な免許もありますが、ここでは小売目的の免許取得を前提に解説します。
許可取得までの流れ
酒類販売免許の申請は、基本的に**税務署(正確には“管轄の酒類指導官がいる所轄税務署”)**に対して行います。以下は一般的な流れです。
✅ 1. 事前相談(税務署への相談)
- 申請予定地・販売方法・申請者情報などを説明
- 「どの免許に該当するか」を確定させる重要なステップ
✅ 2. 書類の準備・提出
- 事業計画書、販売場の見取り図、財務資料、本人確認資料など多数
- 法人の場合は定款・登記簿謄本、役員の履歴書等も必要
✅ 3. 審査(1〜2か月程度)
- 財務状況、人的要件、場所の適格性を中心にチェックされる
- 場合によっては実地確認・ヒアリングがある
✅ 4. 免許の交付
- 無事交付されると、晴れて「販売開始」が可能に
審査で見られる3つのポイント
① 人的要件(経歴や信頼性)
- 申請者に前科がないこと
- 税金の未納がないこと
- 酒類販売に関して十分な知識と適正があると認められること
② 場所的要件(販売場の明確さ)
- 倉庫・事務所・店舗の区分けが明確であること
- 登記や契約が明確になされていること
- 他業種と併用する場合でも、販売スペースが明示されていること
③ 経済的要件(経営の安定性)
- 一定の資金力・収支計画の妥当性
- 赤字続きの会社や事業計画が曖昧なケースはNG
飲食店営業との違いに注意!
「うちは飲食店の営業許可を持っているから、お酒も売れるはず」と思いがちですが、それは**“店内で提供する”ことに限られます。**
飲食店の営業許可=店内での提供(ビール・日本酒など)には問題なし
→ しかし、「持ち帰り販売」や「通販」は別の免許が必要
つまり、提供と販売では法律が違うのです。
当事務所ができること|“はじめての申請”も安心サポート
行政書士高見裕樹事務所では、酒類販売免許の申請について以下の業務を一括対応しています。
✅ 対応業務一覧
- 税務署への事前相談代行
- 必要書類のチェックリスト化と収集支援
- 事業計画書の作成支援(内容補強・構成整理)
- 財務書類の整理・解説(会計士・税理士と連携)
- 販売場の見取り図・レイアウト図の作成
- 提出書類の製本・提出代行
- 補正指導(修正依頼)への対応フォロー
こんな方はぜひご相談ください
- ネットショップで酒類を販売したい
- 飲食店で地酒の販売を始めたいが、免許が必要なのか分からない
- 自社商品の通販を始めたいが、何から準備すべきか分からない
- 個人で酒販事業を始めたいが、事業計画に自信がない
- 申請に時間を割けないので、書類ややり取りをすべて任せたい
よくある質問(FAQ)
Q:実店舗がなくても酒類販売免許は取れますか?
→ 通信販売免許であれば、店舗を構えずに倉庫・事務所のみでも可能です。ただし、保管スペースや配送体制が整っていることが前提となります。
Q:販売できる酒類の種類に制限はありますか?
→ 一般的には制限はありませんが、特定の輸入品や未成年への販売管理などは要注意です。
Q:許可までにどれくらいの期間がかかりますか?
→ 書類の準備に1~2週間、税務署の審査に約2ヶ月が標準的です。
当事務所の対応エリア・特徴
行政書士高見裕樹事務所では、以下の地域での申請実績があります。
- 石川県(金沢市・白山市・野々市市・小松市・加賀市など)
- 富山県(富山市・高岡市・射水市など)
- 福井県(福井市・敦賀市・鯖江市など)
また、酒販免許と一緒に「食品営業許可」や「輸出関連の届出」など複数の申請を同時に進めることも可能です。
まとめ|まずは“このビジネスでお酒を売っていいか?”の確認から
酒類販売免許の申請は、事業モデルと免許種別のマッチングが何より重要です。
どの免許に該当するか、申請が通る内容になっているか、不足している要件は何か──
それらを事前にしっかり確認・設計しておくことが、成功するための第一歩です。
お問い合わせはこちら
📍行政書士高見裕樹事務所
📞 076-203-9314
✉ お問い合わせフォーム:
👉 https://takami-gs.com/contact/