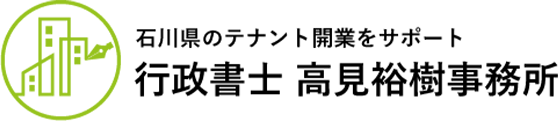第1章|建設業許可ってそもそも何?
“軽微な工事なら不要”の落とし穴
建設業を始めようと思ったとき、まず最初にぶつかるのが「建設業許可って本当に必要なの?」という疑問かもしれません。
実は、建設業はすべての業者が許可を取らなければならないわけではありません。
しかし、この「不要」の解釈を間違えると、思わぬトラブルや営業停止につながるケースもあるため、正しく理解しておくことが大切です。
■ 建設業許可が「必要な場合」と「不要な場合」
建設業法では、一定の金額以下の工事のみを請け負う場合に限り、建設業の許可は不要とされています。これを「軽微な建設工事」と呼びます。
【軽微な建設工事の定義】
- 建築一式工事の場合
→ 工事1件の請負金額が 1,500万円未満(消費税込)
または、木造住宅で延床面積が150㎡未満 - 建築一式工事以外(内装・設備など)
→ 工事1件の請負金額が 500万円未満(消費税込)
この基準を超える工事を1件でも受注する場合は、建設業許可が必須となります。
■ 「許可がいらないから」と安易に始めるのはNG
「最初は小さい仕事だけだから…」と無許可でスタートする業者さんも少なくありません。
しかし、次のようなリスクがあります:
- 元請や取引先から「許可番号」を求められ、契約できなくなる
- 500万円以上の工事をうっかり請けてしまい、無許可営業(違法)扱い
- 銀行融資・補助金・公共工事などに応募できない
一度でも無許可で許可対象の工事を行うと、**罰則(営業停止・罰金等)**の対象になることも。
「まだ小規模だから大丈夫」は大きな落とし穴です。
■ 建設業許可の種類は「業種ごと」&「知事or大臣」で分かれる
さらに注意すべきは、建設業許可は一律ではないという点です。
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| 業種別の許可 | 29種類の専門工事(内装仕上・大工・電気など)から、事業内容に合った業種の許可が必要 |
| 知事or大臣の区分 | 1つの都道府県で営業 → 「知事許可」、複数都道府県に営業所 → 「大臣許可」 |
「うちは内装だけだから簡単でしょ?」と思っても、実際には業種区分が違う場合もあります。
業種の特定や書類の準備をスムーズに進めるためにも、行政書士などの専門家への相談がおすすめです。
■ 石川県での許可申請の特徴とは?
石川県(金沢市・白山市・小松市など)で建設業許可を取得する場合、
申請窓口は石川県庁 建築住宅課 建設業担当となります。
都市部に比べ、申請から許可までの期間がやや短い傾向にあり、早期営業スタートを目指す方にも有利な環境です。
また、当事務所では「建設業許可 × 法人設立」「建設業許可 × 農地転用」など、複合案件にも柔軟に対応しています。
次章では、「そもそもなぜ今、建設業許可が必要なのか?」について、
実務的な観点から掘り下げてご紹介します。
第2章|なぜ今、建設業許可が必要なのか?
信用力・元請け案件・下請け確保の観点から
建設業許可を取得する目的は、単に「法律で決まっているから」というだけではありません。
むしろ、経営戦略として取得するメリットが非常に大きいのが建設業許可の特徴です。
ここでは、実際にお客様から寄せられる声や実務でのニーズをもとに、「なぜ今、許可取得が重要なのか?」を解説します。
■ 1. 元請け・下請けとの契約で“許可番号”を求められる
建設業界では、取引先となる元請会社やハウスメーカー、ゼネコンなどが、
下請業者を選定する際に「建設業許可を持っているかどうか」を最初の選定基準にすることが一般的です。
たとえば…
- 見積書に「建設業許可番号」を記載する欄がある
- 許可がなければそもそも現場に入れない
- 大手案件は「建設業許可があること」が必須条件になっている
つまり、仕事の選択肢を増やす=許可の取得が前提という構図です。
■ 2. 公共工事・補助金・助成金の対象になる
許可業者であれば、以下のような制度にも参加可能となります。
- 公共工事の入札(建設C・Dランクの小規模案件など)
- 地域の空き家改修や耐震補強に対する補助金
- 小規模修繕等契約希望者登録制度(自治体)
これらの制度は無許可ではエントリー不可であり、
建設業許可を取得しておくことで将来的な事業の拡大にもつながります。
■ 3. 銀行や保証協会の審査でも“信用の証”になる
銀行融資やリース契約の際、金融機関は建設業許可の有無を必ず確認します。
- 法人登記簿謄本+建設業許可通知書が信用材料になる
- 工事請負契約書+許可番号が収入計画の裏付けになる
- 保証協会(日本商工会議所など)の信用保証枠が拡がる
つまり、資金調達の場面でも“事業の信頼性”を示す重要書類となるのです。
■ 4. 人材募集・協力業者の確保にも効果的
建設業の人材不足が叫ばれるなか、求人媒体や求人票に「建設業許可取得済」と明記することで、
- 応募者に対する信頼性UP
- 協力業者からの問い合わせ増加
- 職人や一人親方との“横のつながり”が強化される
といった効果が期待できます。
■ 5. 許可を持っていないと「下請法違反」「脱法スキーム」になる可能性も…
稀に見かけるのが、無許可のまま500万円以上の工事を“分割契約”で乗り切るパターンです。
しかしこれは建設業法の脱法行為と判断されるリスクがあり、行政指導や取引停止の対象になる可能性も。
また、元請けとして請け負っている側も、知らずに違反業者を使っていた場合、監督処分の対象になることがあります。
■ 許可は“対外的な信用力”そのもの
このように、建設業許可は単なる書類の話ではなく、
「企業の信頼性」「仕事の幅」「収益性」を左右する、まさに事業の“インフラ”とも言えるものです。
次章では、実際に石川県で建設業許可を取得する際の流れや窓口について解説していきます。
第3章|石川県での建設業許可申請の流れ
提出先と地域別の対応
建設業許可は全国共通の法律に基づいていますが、申請の窓口や提出形式、運用の細部は都道府県ごとに異なります。
ここでは、石川県内で建設業許可を取得する際の流れについて、地域特性を踏まえて詳しく解説します。
■ 石川県の申請先と管轄
石川県内に本店を構える事業者が建設業許可(知事許可)を申請する場合、石川県庁 建築住宅課 建設業係が主な提出先となります。
【提出先(知事許可の場合)】
石川県庁 建築住宅課 建設業係
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
TEL:076-225-1773
※郵送または持参にて提出。事前予約や書類の仮確認制度もあり。
なお、大臣許可を申請する場合(複数都道府県に営業所がある場合)は、北陸地方整備局が窓口となります。
■ 申請のステップは大きく5段階
- 要件確認(5要件+業種選定)
→ 経営業務管理責任者・専任技術者などの配置が必要です - 必要書類の収集・作成
→ 申請書・誓約書・登記簿謄本・決算書・役員の履歴書など - 石川県庁に書類提出
→ 仮受付→本受付→審査スタート - 県の審査・補正対応(約4〜6週間)
→ 内容に不備がある場合、電話やメールで補正依頼あり - 許可通知書の受領・許可番号の取得
→ 通知が届いた日が「許可年月日」となります
■ 金沢市・小松市・白山市などの地域別傾向
石川県は都市部と郊外で業種ニーズや申請傾向に若干の違いがあります。
- 金沢市エリア
→ 電気・内装・とび土工など都市型の業種が多い
→ 提出書類の記載ミスや印鑑忘れがあると補正連絡がすぐ入る - 小松市・能美市・加賀市
→ 土木・舗装・解体業の割合が多く、決算書類の整備が肝心 - 白山市・野々市市・河北郡
→ 工務店や建築一式での申請が多く、経管や実務経験の証明がネックになることも
■ 「石川県ならでは」の注意点とは?
石川県では、次のような実務的ポイントも押さえておく必要があります。
- 役員の住民票の取得先(本籍地記載)
- “直前5年”の実務経験を証明する資料の整備
- 個人事業主から法人成りの場合の引き継ぎ書類の添付
また、申請者が元請け業者の下請実績を主張する場合、元請からの証明書(請書・注文書など)が必要となるため、事前に相談・準備しておくことが重要です。
■ 行政書士を活用した“スピード申請”も可能
当事務所では、以下のようなサービスを提供しています:
- 書類収集・役員の履歴確認・添付書類の代理取得
- 法人設立と同時申請プラン(会社登記+許可申請)
- 実務経験の証明資料作成サポート(元請とのやり取り代行)
- 許可後の変更届・決算変更届の定期対応プラン
「急ぎで取りたい」「自分でやるのは不安」「何をどう準備すればいいかわからない」という方には、トータルサポートでの申請代行が最も効率的です。
次章では、実際の審査に最も影響する「許可取得の5大要件」について詳しく解説していきます。
第4章|許可取得の5大要件
“経管・専技・財産・誠実・欠格”とは何か?
建設業許可を取得するには、法律で定められた「5つの要件」を満たしている必要があります。
これは全国共通で、石川県でも当然ながらこの5項目のチェックが審査の中心になります。
以下、それぞれの要件について、実務上の注意点やよくあるつまずきポイントも含めて詳しく解説します。
■ 要件1:経営業務の管理責任者(経管)
経管とは、申請者(法人であれば役員、個人であれば本人または支配人)に、過去5年以上の建設業の経営経験があることを求める要件です。
【認められる例】
- 建設会社の取締役として5年以上在任
- 個人事業主として5年以上連続して建設業を営んでいた
- 建設会社の支店長・営業所長として一定の裁量を持っていた
【ポイント】
- 登記簿謄本や確定申告書、請負契約書などの証明資料が必要
- 一時的なブランクがあると「通算年数」として扱えないケースも
- 経営経験は業種を問わず建設業であればOK(例:内装業→電気工事業へ申請も可能)
■ 要件2:専任技術者(専技)
専技とは、許可を受ける各業種ごとに、一定の技術的資格または実務経験を持つ人物を常勤で配置する必要があるという要件です。
【該当する例】
- 建築士、施工管理技士、電気工事士などの国家資格保有者
- 実務経験10年(または7年+学歴)のある者
- 上記資格者がフルタイムで事業所に勤務している場合
【注意点】
- 同一人物を“経管と専技”の兼務は可能ですが、常勤性に注意
- 電気・管・建築一式などでは学歴・経験年数の証明に時間がかかる場合も
- 実務経験の証明には、元請からの注文書・請書・工事写真などが必要な場合あり
■ 要件3:財産的基礎(資金要件)
原則として、次のいずれかを満たしている必要があります。
- 自己資本が500万円以上ある(直近の決算書で確認)
- 500万円以上の資金調達能力がある(預金残高証明書など)
- 新規設立で500万円以上の資本金を有している
【実務上の対策】
- 赤字決算が続いている場合は“資産超過”であるかの確認を
- 金融機関の残高証明書の発行日が申請日から近い日付であることが重要
- 法人成りしたてでも、資本金500万円あれば問題なし
■ 要件4:誠実性
「過去に違法・不正行為がなかったか」「契約を履行する誠実な体制が整っているか」を確認するものです。
【チェックされる主な内容】
- 役員・支配人などが過去に法令違反や刑罰を受けていないか
- 社会保険・労働保険などに未加入・未納の事実がないか
- 建設業に関する行政処分歴がないか
【注意点】
- 役員が過去に他社で不正行為に関与していた場合、影響することがある
- 虚偽の申請をした場合は許可取消の対象になるため慎重に
■ 要件5:欠格事由に該当しないこと
建設業法では「このような人は許可を与えない」と定めた“欠格事由”が複数あります。
【主な欠格事由】
- 成年被後見人・破産手続中の者
- 禁錮以上の刑に処された者(5年以内)
- 許可取消後、5年を経過していない法人・個人
- 暴力団関係者やその影響下にある場合
【実務の注意】
- 申請者だけでなく役員・支店長・営業所長も対象になる
- 法人の役員変更や支配人設置届なども随時チェックされる
以上の5要件は、どれか1つでも欠けていれば許可が出ないという極めて重要なポイントです。
当事務所では、要件の事前チェック無料相談も受け付けております。
次章では、建設業許可の中でも特に注意すべき「500万円の壁」や実際の工事規模との関係性について詳しく解説していきます。
第5章|500万円未満の工事でも許可が必要?
“軽微な工事”の定義と落とし穴
「ウチは小さなリフォームしかやらないから、建設業許可はいらないよ」と考えている方も少なくありません。
しかし実際には、金額や工種の区切り方を誤ると“無許可営業”とみなされるリスクがあり、注意が必要です。
■ 軽微な工事の定義(建設業法第3条)
建設業許可が不要なケースは、法律で以下のように定められています。
【建設一式工事】
- 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)
- かつ木造住宅で延べ面積150㎡未満
【建設一式工事以外(内装・電気・水道等)】
- 1件の請負代金が500万円未満(税込)
つまり、リフォーム業者や塗装業者など「一式工事ではない」業種は、500万円を超える工事を請け負う場合には必ず建設業許可が必要になります。
■ 「材料費込み」で金額をカウントする
ここで見落とされがちなのが、金額の算定方法です。
「うちは人工(にんく)だけで50万円。材料費は施主が負担したから関係ないでしょ?」
と思っていると要注意です。
建設業法上は“請負契約の総額(税込)”が500万円を超えたらアウト。
材料費・機材費・諸経費すべてを含んで判断されます。
■ 実際の違反例と罰則
無許可で工事を請け負った場合、違反が発覚すると営業停止や罰金刑、刑事処分の対象になります。
【違反例】
- 許可を持っていない業者が、500万円を超える内装工事を受注
- 知人経由で元請から頼まれ、材料費+工賃で600万円となった事例
- 「複数の契約に分けた」つもりが、実質的に一体の工事と判断された例
【罰則】
- 無許可営業:懲役3年以下または罰金300万円以下(法人は1億円以下)
■ 「500万円未満に収める」リスク
「許可がないから、500万円に抑えた契約書を作ろう」と意図的に設計してしまうケースもありますが、これは非常にリスクが高いです。
- 施主が契約に不満を感じてトラブルになる
- 実際の工事金額と契約書の記載が一致しない
- 税務調査・保険・瑕疵トラブルで後から発覚
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、しっかりと許可を取得して正規の契約を交わすことが事業者にとっての信用力強化にもなります。
■ 建設業許可があることで得られる信用と受注力
許可を持っていることで、次のようなビジネス上のメリットが得られます。
- 大手ハウスメーカーや官公庁工事への入札が可能になる
- 下請けとしての信頼性が高まり、元請との取引がスムーズに
- 住宅ローン審査で「建設業許可のある会社」の証明が必要なケースにも対応可
■ 当事務所からのアドバイス
石川県では、比較的中小規模のリフォーム業者様が多く、「500万円ラインぎりぎり」の工事をしているケースが多数見られます。
不安な場合は、**「1件500万円未満でも将来的に超える可能性があるか」**を事前に想定して、早めに建設業許可の準備を始めるのが賢明です。
次章では、許可を取得した後に必要となる「定期的な届出」や「許可更新の流れ」について詳しく解説していきます。
第6章|許可を取った後に必要な手続きとは?
毎年の届出・5年ごとの更新のポイント
建設業許可を取得したら、それで終わり――ではありません。
むしろそこからが本番です。
許可を「維持」し、信用を積み上げていくためには、**毎年の「決算変更届(事業年度終了報告書)」**と、**5年ごとの「許可更新」**という2つの大切な手続きを忘れずに行う必要があります。
■ 決算変更届(毎年)
【概要】
建設業許可を取得している業者は、毎事業年度終了後4か月以内に、決算の内容を都道府県知事または国土交通大臣に報告する義務があります。
これは「事業年度終了報告書」とも呼ばれ、「決算変更届」と言われることが多いです。
【提出する書類】
- 事業年度終了報告書
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 工事経歴書
- 使用人数調書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 登記簿謄本(法人の場合)
【注意点】
- 提出しないと次の「更新」ができません
- 決算書類は「建設業用」に修正が必要なケースも
- 新規取得時に提出しなかった「経営事項審査」を受ける場合は、これをベースに審査されます
■ 許可の更新(5年ごと)
建設業許可の有効期限は5年間です。
期限満了日の30日前までに更新申請をしないと、許可が失効してしまい、新たに「新規申請」をやり直さなければならなくなります。
【更新時のチェック項目】
- 経営業務の管理責任者が交代していないか?
- 専任技術者の要件を満たしているか?
- 欠格要件に該当する人物が役員に入っていないか?
- 決算変更届を毎年出しているか?
【行政書士からの実務アドバイス】
- 有効期限は許可通知書に記載されています。事前にカレンダー登録しておきましょう。
- 更新手続きには、役所への郵送ではなく窓口提出を求められる自治体も多くあります(石川県でも一部該当)。
- 更新手続きは、期限の3か月前から受付可能なため、早めの準備が吉。
■ その他の定期的な届出
建設業許可を維持するには、次のような「変更届出」も必要です。
| 変更内容 | 届出期限 | 例 |
|---|---|---|
| 商号・名称の変更 | 30日以内 | 会社名が変わったとき |
| 所在地の変更 | 30日以内 | 本店移転など |
| 役員の変更 | 30日以内 | 新任・辞任含む |
| 経営業務の管理責任者の変更 | 2週間以内 | 引退や交代など |
| 専任技術者の変更 | 2週間以内 | 配置替えや退職など |
【ポイント】
これらを出さずに放置していると、更新時に「記載内容が実態と異なる」とされて、手続きが遅れたり、最悪の場合、許可が取り消されることもあります。
次章では、実際に当事務所で対応した「許可取得の成功事例」や「審査で苦労したケース」を紹介しながら、リアルな実務の様子をご紹介します。
第7章|当事務所のサポート事例紹介
“初めての許可取得”をどう乗り越えたか?
建設業許可の申請は、法的な条件に加え、実務的なハードルも非常に高い手続きです。
「建設業を始めて10年、そろそろ許可を取りたい」「法人化したので、ちゃんと許可を取って事業を広げたい」という方からのご相談が日々寄せられています。
ここでは、行政書士高見裕樹事務所がこれまでに手がけた「実際の事例」をもとに、どのように課題を乗り越え、許可取得に至ったのかをご紹介します。
■ 事例①|個人事業主から法人化し、初めての許可取得(内装工事業)
- 【依頼者】金沢市の内装工事業者(従業員3名)
- 【課題】個人事業主として活動してきたが、法人化を機に元請案件を増やすため許可を取りたい
- 【ハードル】
- 経営業務の管理責任者が設立直後で、実績証明が難しい
- 工事経歴書の書き方がわからない
- 専任技術者として登録できる資格者が社内に1名しかいない
【対応内容】
- 以前の個人事業時代の実績を元に、**「実務経験証明書」**を丁寧に作成
- 確定申告書の写しや請求書・契約書などをセットにして、証拠性を補強
- 工事経歴書は、当事務所でヒアリングのうえ記載内容を作成
- 技術者の国家資格証明や職歴確認書を整備
▶ 無事に新規取得完了。
現在では、元請けからの工事依頼が増加し、公共案件の入札も視野に入れているとのことです。
■ 事例②|“許可が取れない”と言われた業種でも取得できた(塗装+防水)
- 【依頼者】能美市の小規模塗装業者
- 【課題】業界団体から「うちは防水業はダメ、塗装だけにして」と言われ諦めていた
- 【ハードル】
- 業種の分類が微妙で、申請にどの業種を選ぶかが問題
- 技術者の経験年数がぎりぎり
【対応内容】
- 複数の工事実績から、「塗装工事」ではなく「防水工事」でまとめ直す方針を提案
- 過去の現場写真・請負契約書・見積書を時系列で整理
- 技術者の経験についても、過去勤務先の元請業者から証明を取得
▶ 「防水工事業」で建設業許可を新規取得。
実際には「塗装+防水」を一体でやっていたため、業種の切り分けで審査官との協議が鍵となりました。
■ 事例③|専任技術者の退職で更新できなくなりかけたが…
- 【依頼者】白山市のリフォーム会社(法人)
- 【課題】更新申請の直前に、専任技術者が退職
- 【ハードル】
- 代替の技術者が社内にいない
- 更新期限まで時間がない
- 決算変更届も未提出が2年分
【対応内容】
- 緊急で別の従業員の実務経験を調査し、10年以上の実務証明で対応
- 過去の請負契約・作業日報・納品書を取りまとめ、補強資料として提出
- 決算変更届も一括で整備し、更新申請と同時提出
▶ 期限ギリギリで無事に更新完了。
「建設業許可の更新には、技術者と書類管理の両輪が必要」と痛感されたとのことでした。
■ 実務の現場では「グレーゾーン」が多い
これらの事例に共通しているのは、法律上の要件だけでなく、“現場の実務とのすり合わせ”が必要になるという点です。
建設業許可の審査は、担当者によって判断基準にばらつきがあり、
「この書類では足りない」「この証明方法は認められない」など、やり直しを求められるケースもあります。
だからこそ、地元に精通した行政書士と連携し、警察署・県庁などとの事前調整を行うことが成功のカギとなります。
次章では、こうした許可取得をスムーズに進めるために、行政書士に依頼するメリットや費用感、依頼すべきタイミングなどを解説していきます。
第8章|行政書士に依頼するメリットとは?
費用感・対応範囲・トラブル回避
建設業許可の取得や更新は、自分で申請できる制度ではあります。
しかしながら、実際には多くの事業者様が行政書士に依頼しているのが実情です。
では、なぜ行政書士に頼むべきなのでしょうか?
ここでは、費用感・対応範囲・トラブル回避の3つの視点から、依頼するメリットを整理します。
■ メリット①|手続きのスピードと正確性
建設業許可の書類はとにかく多く、そして複雑です。
- どの業種を申請すべきか
- 経営業務の管理責任者の要件をどう証明するか
- 技術者の実務経験を何年と認定されるか
- 決算書を「建設業仕様」にどう直すか
こうした判断を誤ると、何度も役所から差し戻されて、開業スケジュールがズレる原因になります。
行政書士に依頼することで、最短ルートでの許可取得が目指せます。
■ メリット②|実務をふまえた“調整力”
例えば「この証明書で通る?」「この業種で大丈夫?」といったグレーなケースに直面したとき、行政書士は次のように動きます。
- 審査する県庁の建設業担当部署に事前相談を実施
- 必要な補強資料を提案
- 記載方法や証明方法を調整・代案を提示
「出してみないとわからない」ではなく、「出す前に通す準備を整える」――これがプロの仕事です。
■ メリット③|更新・変更の“漏れ”を防げる
許可を取った後の以下の手続きを忘れると、致命的なリスクになります。
| 手続き | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 決算変更届 | 毎年の事業年度終了後 | 4か月以内 |
| 更新手続き | 許可の有効期限 | 5年ごと |
| 変更届 | 役員や所在地の変更 | 原則30日以内 |
当事務所では、定期点検のアナウンスや書類管理も代行しています。
「気がついたら許可が失効していた」――そんな事態を防げるのが大きなメリットです。
■ メリット④|ワンストップ対応が可能(物件・図面・改装まで)
行政書士高見裕樹事務所では、建設業許可の取得だけでなく、以下のような周辺業務もワンストップで対応しています。
- 法人設立(株式会社・合同会社)
- 定款作成・印鑑証明取得
- 建設業の事業計画書作成
- 不動産・事務所物件の紹介(ふちどり不動産)
- 内装工事・施工(提携業者 or 自社施工)
→ つまり、「開業支援」まで一括でお任せいただけます。
■ 費用の目安
※あくまで参考価格です。詳細は個別に見積もりいたします。
| 項目 | 行政書士報酬 | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 新規取得(知事許可・一般) | 150,000〜250,000円 | 90,000円(石川県) |
| 更新手続き | 70,000〜120,000円 | 50,000円 |
| 決算変更届(単年) | 30,000〜50,000円 | なし |
| 変更届(役員・住所等) | 15,000〜30,000円 | なし |
■ 実際に依頼されるお客様の声
- 「自分でやろうとしたら2か月かかったのに、お願いしたら3週間で完了しました」
- 「途中で要件に該当しないと言われかけたけど、補強資料で通してもらえて助かった」
- 「面倒な届出も全部やってくれるので、営業に集中できる」
次章では、よくある質問や誤解、そして実際のトラブル例を取り上げながら、建設業許可に関するQ&A形式でのまとめを行います。
第9章|よくある質問と注意点まとめ
許可要件・トラブル事例・Q&A
建設業許可の取得を検討するうえで、よくある質問や誤解、実際にトラブルにつながりやすいポイントをQ&A形式でまとめました。
Q1|建設業許可がなくても工事はできるの?
A. はい、「軽微な工事」であれば許可がなくても請負可能です。
ただし以下の金額を超えると、許可が必須になります。
| 工事の種類 | 許可が不要な上限 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件あたり1,500万円未満(消費税抜) |
| その他の工事 | 1件あたり500万円未満(消費税抜) |
※「税込」で請けてしまうと超えてしまうこともあるため注意が必要です。
Q2|個人事業主でも建設業許可は取れる?
A. 可能です。
個人事業主でも要件を満たせば許可取得が可能です。ただし、以下の点が法人よりも難しくなりがちです。
- 経営業務の管理責任者としての経験を証明する資料が乏しい
- 決算書が「簡易な収支内訳書」になっていることが多い
- 技術者が代表者本人のみで、専任性を確保しづらい
→ 行政書士による資料補強や構成の工夫が必要です。
Q3|許可取得後の「決算変更届」って毎年必要?
A. はい、毎年1回必須です。
事業年度終了後4か月以内に提出することが義務付けられており、忘れると次回の「更新」や「業種追加」ができなくなります。
→「決算変更届を5年間出していない」=更新できず許可が失効するケースも多発しています。
Q4|過去に無許可で工事を請け負っていたら許可は取れない?
A. 原則として直ちに不許可にはなりませんが、状況に応じて判断されます。
- 過去に「無許可営業」として行政指導・処分を受けていれば、欠格事由になる場合があります
- 申請時に「軽微工事のみ請けていた」との説明と証明が必要になることも
→ 不安な場合は、事前に行政書士によるヒアリング・整理を行うのが安全です。
Q5|役所に直接申請しても、同じように許可が出る?
A. 結果は同じでも、手続きのスピードや完成度が大きく変わります。
- 自分で提出→不備→再提出→補正→審査長期化
- 行政書士経由→事前相談→一発受理→審査期間短縮
→ 結果として、開業日が1か月以上早まるケースもあります。
実際によくある“見落とし”ポイント
- 専任技術者が複数の事業所を掛け持ちしていた
- 決算変更届を2年連続未提出
- 経営業務の管理責任者が実質的に不在(名義貸し)
- 許可が切れていたのに公共工事を請け負っていた
→ いずれも大きなトラブルにつながるケース。定期的なチェックが必要です。
次章(最終章)では、行政書士高見裕樹事務所におけるサポート内容を改めてまとめ、お問い合わせへの導線とともにご案内いたします。
第10章|まとめとお問い合わせ案内
まずはご相談からスタート!
建設業許可は、一見ハードルが高そうに見えて、実は“正しい順序”と“要件の整理”さえできれば、スムーズに取得できる許可です。
とはいえ――
- 自社の体制で本当に要件を満たせるのか不安
- 決算書の整理や技術者の証明でつまずいてしまいそう
- 書類を準備する時間がない
こうしたお悩みをお持ちの方も多いと思います。
だからこそ、専門の行政書士に“最初から丸投げ”してしまうのが、最も効率的な選択です。
✅ 行政書士高見裕樹事務所の強み
石川県金沢市にある当事務所は、建設業許可をはじめとした各種許認可申請に強みを持つ行政書士事務所です。
\「来るもの拒まず」「とことん本気で向き合う」方針がモットーです/
当事務所では、以下のようなサポートが可能です:
- ✅ 経営業務の管理責任者・専任技術者の要件診断
- ✅ 必要書類のチェックリスト化&収集サポート
- ✅ 決算書の建設業仕様への再構成サポート(会計事務所との連携可)
- ✅ 知事・大臣許可/一般・特定/新規・更新・業種追加いずれにも対応
- ✅ 法人設立や事務所物件紹介もワンストップ対応(ふちどり不動産連携)
- ✅ 土日祝・夜間対応も柔軟に相談可
✅ 建設業許可が「営業力」に変わる時代
建設業界では、元請との取引条件として「許可取得」が求められることも少なくありません。
- 入札参加資格の獲得
- 補助金・助成金の申請時の加点
- 法人としての社会的信用力の向上
このように、建設業許可は“単なる許可”ではなく、経営戦略としても非常に有効なツールなのです。
✅ ご相談・お問い合わせはこちらから
「建設業許可を取りたいけれど、何から始めればよいかわからない」
そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。
📞【電話】076-203-9314
🌐【ホームページ】https://takami-office.net/
✉️【お問い合わせフォーム】「行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせ」で検索!
石川県内(金沢市・白山市・小松市・能美市・野々市市など)を中心に、富山県・福井県にも対応可能です。
\建設業許可のことなら、まずは私たちにご相談ください!/
不動産・建設・許認可のスペシャリストが、あなたの事業を全力でサポートします。