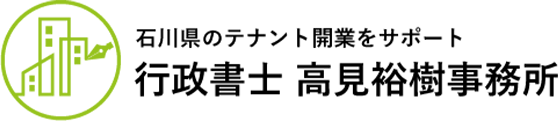第1章|旅館業法とは?
民泊との違いと「簡易宿所」の位置づけ
◆ 「宿をやりたい」は許可が必要です
空き家や自宅の一部を使って、観光客に泊まってもらう――
そうしたいわゆる「民泊」や「簡易宿」は、旅館業法という法律の規制対象になります。
旅館業法に基づく「許可」を受けなければ、たとえ1人1泊でも宿泊料を取って泊めることはできません。
無許可で営業した場合は、**罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)**の対象にもなります。
◆ 旅館業法で定める“宿泊”とは?
旅館業法では、「宿泊」を以下のように定義しています:
“宿泊とは、寝具を使用して施設を利用すること”
(※日帰り利用や仮眠、ベッドや布団のない施設は含まない)
つまり、以下のようなケースも「宿泊」に該当し、旅館業の許可が必要です:
- ベッド付きの一室を貸し出す(空き家活用型)
- 自宅の1室に寝具を備え、観光客を泊める(住みながら民泊型)
- アパートの一部をAirbnbで提供する(共同住宅活用型)
◆ 「旅館業」と「住宅宿泊事業(民泊)」の違い
宿を開くには「旅館業法に基づく許可」か、「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)」に基づく届出が必要です。
しかし、多くの自治体では住宅宿泊事業(届出制)に対して非常に厳しい制限がかかっており、実質的には「旅館業許可」を取得する方がスムーズなケースが増えています。
| 区分 | 旅館業(簡易宿所) | 住宅宿泊事業(民泊) |
|---|---|---|
| 根拠法 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法 |
| 必要手続き | 許可(都道府県・市) | 届出(国) |
| 宿泊日数制限 | なし(通年営業可) | 年間180日まで |
| 利用可能建物 | 専用施設(用途変更あり) | 住宅として使用中の建物 |
| 規制 | 保健所・消防・建築基準法・都市計画 | 条例で厳しく制限されている場合が多い |
| 金沢市の場合 | 旅館業を推奨(条例により民泊新法は実質不可能) | 届出は可能でも、ほぼ認可されない運用 |
◆ 「簡易宿所営業」とは?
旅館業許可には4つの類型があります:
- 旅館・ホテル営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
- 特区民泊(※地域限定)
この中で、空き家・自宅の一部・共同住宅などを使って少人数の宿泊施設を開設する場合は、ほぼ例外なく「簡易宿所営業」が該当します。
簡易宿所の特徴:
- 宿泊料を取って人を泊める営業
- 客室が1室でも許可可能
- 受付(フロント)や帳場の設置要件あり(代替措置可)
- トイレ・浴室などの設備基準あり(共用でも可)
- 自宅の一部でも開設可能だが、営業部分と生活部分は明確に区分する必要あり
◆ 金沢市の場合:民泊=旅館業扱い
金沢市では、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出に対して、**厳しい運用(制限区域・住民説明義務など)**がなされており、実務的には旅館業の許可を取る方がスムーズです。
また、以下のような指導基準があります:
- 受付(帳場)や防犯カメラの設置が求められる
- 住居専用地域では営業不可(第一種低層住居専用地域など)
- 条例によって観光地区内でも民泊に制限がある
そのため、簡易宿所営業として開業するほうが、安定的かつ継続的に事業を進めやすいのが現実です。
◆ 「無許可民泊」は取り締まり対象
現在、インターネットでの無許可民泊募集(Airbnb・Booking.com等)に対しては、保健所や観光課、警察が連携して厳しく監視を行っています。
- ❌ 近隣住民からの通報 → 調査
- ❌ 立入検査 → 営業停止命令・刑事告発
- ❌ サイト掲載停止 → アカウント凍結
無許可営業はリスクしかありません。
◆ 旅館業許可は「事業」として将来性がある
簡易宿所は、副業から本業まで幅広く展開可能であり、
- 外国人観光客の増加
- インバウンド回復
- 空き家対策や地域活性化の手段
として、非常に有望な業態です。
しかしその一方で、法律・設備・地域条例への対応が複雑であり、「よくわからないまま進める」と許可が下りなかったり、途中で頓挫してしまうリスクもあります。
第2章|物件選びの注意点
立地・用途地域・構造チェックがカギを握る!
◆ 許可を取れる物件と取れない物件がある
旅館業許可、とくに「簡易宿所営業」は、どの物件でも取れるわけではありません。
「建物があって、泊まる場所があるならいいでしょ?」という感覚で進めてしまうと、用途地域・構造・消防基準などでNGを出され、許可が下りないことがあります。
この章では、旅館業許可における「物件選びで見るべきポイント」を具体的に解説します。
◆ チェック①:用途地域の確認が最重要
まず最初に確認すべきは、「そのエリアで宿泊施設の営業ができるかどうか」です。
これは**都市計画上の「用途地域」**で決まっています。
用途地域とは?
都市にはそれぞれ「住宅向け」「商業向け」「工業向け」など、土地の使い方に応じたエリア分け(用途地域)があります。
旅館業は、用途地域によって営業可否がはっきり分かれます。
主な用途地域と旅館業の可否(目安)
| 用途地域 | 旅館業の可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 商業地域 | ◯ 許可されやすい | 飲食・風俗も可能 |
| 近隣商業地域 | ◯ 基本OK | 住宅との混在地域、住民対策が必要 |
| 準工業地域 | ◯/△ 用途確認必要 | 工場・倉庫との併存地 |
| 第二種住居地域 | △ 条件次第で可能 | 建物規模・住環境配慮がカギ |
| 第一種住居地域 | ✕ 基本不可 | 金沢市は特に厳しい運用 |
| 第一種低層住居専用地域 | ✕ 絶対不可 | 市街化調整区域と同等にNG |
※市区町村により判断基準や緩和措置が異なります。金沢市では特に厳しい傾向があります。
用途地域の調べ方:
- 市役所の都市計画課で「用途地域証明書」を取得
- インターネットの都市計画図を確認(自治体による)
- 不動産会社に聞いても正確とは限らないため、行政書士が代理取得・調査が安心
◆ チェック②:保全対象施設との距離制限
旅館業の許可では、保育園・学校・病院などの“保全対象施設”と一定距離を保たなければならないルールがあります。
これは自治体の旅館業条例や都市条例に定められており、金沢市でも独自の指導基準が設けられています。
金沢市の例(※変動あり):
- 保育園や小中学校などの保全施設から直線100m以内はNG
- 近隣説明や掲示義務が課されることもある
- 審査時に地図上でチェックされ、数メートルでもNGとなるケースあり
◆ チェック③:建物の構造・用途の確認
🏠 建物の「用途」が“住宅”になっていませんか?
建物の登記や固定資産税上の用途が「住宅」になっている場合、原則としてそのまま宿泊施設には使えません。
→ この場合、**「旅館業に適した用途への変更(用途変更)」**が必要になります。
これは建築基準法に基づく正式な変更手続きであり、建築士や設計事務所と連携するケースがほとんどです。
🛏 寝室の数、玄関の数、トイレの配置も要チェック
簡易宿所では、宿泊者が使用する寝室(客室)・玄関・トイレ・浴室などの最低限の構造基準があります。
- 客室には十分な換気・採光・天井高さが必要
- トイレや浴室は共同でもOKだが、清潔で機能的な配置が求められる
- 家主と宿泊者の生活空間が混在しないこと(ゾーニング)
◆ チェック④:消防法への適合状況
「この家、きれいだし広いから宿に使えそう!」
と思っても、消防設備が不足していると絶対に許可は下りません。
消防署のチェックポイント:
- 火災報知器の設置(連動式の自動火災報知設備)
- 避難経路・誘導灯の設置
- 消火器の数と配置
- 非常口の確保と表示
※延床面積や客室数によっては、消防設備士による設計が必要な場合もあります。
◆ チェック⑤:金沢市の条例・指導基準
金沢市では、観光都市としての景観保全や住民環境への配慮から、独自の条例・ガイドラインを設けています。
例:
- 看板・照明・屋外広告は制限される(景観条例)
- 「住民説明」「周辺同意」などを求められることがある(特に町家や住宅街)
- 町家などは「伝統的建築物」として保存規制がかかっている場合も
◆ 「物件を決める前」に相談を!
ここまで見てきたように、物件を決めてから「許可が下りない」と判明するのは大きな損失です。
- 賃貸契約の初期費用
- 取得した不動産の価値
- リフォーム費用
- オープン予定のスケジュール
すべてが崩れてしまうこともあります。
だからこそ、最初の段階で行政書士に相談することが重要です。
「この物件で旅館業ができるのか?」を、法的・実務的に判断することが、最短ルートです。
第3章|旅館業許可申請の全体フローと必要書類
書類の整備から現地確認まで、許可取得までのステップを完全解説!
◆ 旅館業許可申請の「全体の流れ」
旅館業(簡易宿所)の許可は、「とりあえず書類を出せばよい」というものではありません。
建物・図面・設備・地域条件・行政手続の5つを“連携”させて許可まで進める必要があります。
石川県金沢市の場合の流れを例に、許可取得までの基本フローをご紹介します。
🔽 旅館業許可取得の基本フロー(簡易宿所の場合)
| ステップ | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| ① 事前相談 | 行政書士・保健所・消防署との相談 | 行政によっては予約制・複数回必要 |
| ② 図面作成 | 平面図・立面図・設備図・求積図など | 建築士・行政書士が監修することが望ましい |
| ③ 消防協議 | 消防設備の確認・着工前に協議 | 連動式火災報知器などを事前計画 |
| ④ 工事・設備設置 | 内装工事・消防設備・看板設置など | 申請書と図面に一致させる必要あり |
| ⑤ 保健所へ申請 | 申請書+図面+誓約書等を提出 | 原則、保健所窓口への持参(電子不可) |
| ⑥ 現地確認 | 保健所の立入検査(検査日調整) | 事前に自主管理チェックが必須 |
| ⑦ 許可証交付 | 合格後に許可証が交付され、営業可能に | 通常1~2週間程度で交付 |
◆ 申請時に必要な主な書類(石川県・金沢市の例)
【1】施設関係書類
- 施設の平面図(縮尺付き・寸法入り)
- 客室・共用部の求積図(面積表示)
- トイレ・浴室・台所・玄関などの配置図
- 防火設備・避難経路・誘導灯の配置図
- 写真(外観・玄関・トイレ・浴室・客室など)
【2】営業者関係書類
- 営業許可申請書(所定様式)
- 誓約書(欠格事由に該当しない旨)
- 使用承諾書(賃貸物件の場合)
- 建物登記事項証明書(法務局)
- 用途地域証明書(都市計画課)
- 住民票(個人申請の場合)/法人登記簿謄本(法人申請の場合)
【3】その他必要書類(必要に応じて)
- 消防同意書・設備図面(消防協議済の証明)
- 建築士の確認書・用途変更完了届(構造変更した場合)
- 古民家や町家の場合は景観法関係の届出も必要
◆ 審査期間と許可取得までの時間感覚
金沢市での簡易宿所営業許可は、概ね申請から20〜30日前後で交付されるケースが多いです。
ただし、以下の状況では時間が延びることがあります:
- 消防設備の設置が間に合っていない
- 図面と現地が不一致(例:図面にない壁がある)
- 古民家・町家等で景観規制や構造特例申請が必要な場合
- 保健所側のスケジュール混雑(観光シーズン前など)
▶ 申請~営業開始まで、1〜1.5か月程度を見ておくのが安全です。
◆ 内装と図面は“完全一致”が必要
旅館業許可の審査では、提出された図面と実際の内装が完全に一致していることが求められます。
たとえば:
- 図面にない壁を後から設置 → 構造変更扱いで検査NG
- 客室の面積が図面より狭い → 床面積要件に満たず不合格
- 写真と実際が違う → 現況変更の疑いで再検査
▶ 図面作成は建築士・行政書士と連携して、許可取得を前提に描くことが鉄則です。
◆ 現地検査で見られる主なポイント
保健所職員による現地確認(立入検査)では、次のようなチェックが行われます。
| 項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 客室 | 換気・採光・清掃状況・面積基準(原則7㎡以上) |
| トイレ | 清潔性・手洗い設置・男女別でなくても可 |
| 浴室 | 共同浴室・ユニットバスも可/給湯設備の有無 |
| 台所(必要な場合) | 宿泊者用の炊事施設があるか |
| 帳場(受付) | 簡易宿所には原則必要/代替措置でも可(施錠付き玄関+管理者常駐など) |
| 防火・避難設備 | 火災報知器・誘導灯・消火器の設置確認 |
◆ NGにならないためのポイント
- ✅ 申請前に現地チェックを行う(行政書士同行推奨)
- ✅ 現地で修正できない部分(構造・面積)は図面段階で確認
- ✅ 検査直前のセルフチェックリスト活用でミスを防ぐ
- ✅ 許可前にネット掲載・予約受付をしないこと!
第4章|消防・保健所との連携
“知らなかった”では済まされない基準たち|旅館業許可における2大関門
旅館業許可申請において、行政書士の立場から「最も許可を遅らせる要因」と感じるのが、消防署と保健所との調整不足です。
どちらも申請には欠かせない存在ですが、**「聞いてない」「思っていたより厳しい」**というトラブルが後を絶ちません。
この章では、旅館業許可における消防・保健所の具体的な要求と注意点を詳しく解説します。
◆ 消防署との協議:設計前の“事前相談”がカギ!
🔹 消防法上、旅館業は「特殊用途建築物」に該当
たとえ客室が1室でも、宿泊料を取って寝泊まりさせる場合、建物は消防法上“旅館”扱いとなります。
そのため、以下のような設備の設置が義務となることがあります:
| 設備名 | 概要 | 義務対象の目安 |
|---|---|---|
| 自動火災報知設備 | 感知器+受信機+警報ベル | 延床150㎡超など(要協議) |
| 誘導灯 | 避難方向を示す非常灯 | 2階建以上や客室が複数ある施設 |
| 消火器 | 容量・設置場所を指定 | 全施設義務(間取りで本数変動) |
| 避難経路標示 | 非常口の案内板・表示灯 | 客室が奥まっている場合などに必須 |
| 防火戸・遮煙性能 | 廊下と客室の間の建具に関する規定 | 共同住宅・古民家型では要確認 |
※基準は都道府県・市町村により異なります。金沢市では比較的厳格です。
🔸 「この規模なら報知器だけでOK」は要注意
よくある誤解が、「うちは小さい宿だから火災報知器だけでいいでしょ?」という認識です。
実際には、客室数や避難経路の長さ、延床面積によって設備義務が細かく変動します。
▶ 判断に迷ったら、**着工前に“消防署へ設計図を持って協議”**するのがベストです。
◆ 保健所との調整:生活と営業の“分離”がポイント
旅館業の審査主体は、最終的には保健所です。
特に簡易宿所営業では、住居兼用・自宅利用・空き家改修などのケースが多いため、保健所が“生活空間と営業空間の境界”を厳しくチェックしてきます。
🔹 保健所が見る主なポイント
| 項目 | チェックされる内容 |
|---|---|
| 客室 | 採光・換気・面積(7㎡以上目安)・床材の清掃性 |
| トイレ | 手洗い設置・清掃状態・共同利用の有無 |
| 浴室 | 給湯・排水・カビ・転倒防止対策など |
| 台所 | 簡易宿所では必須ではないが、設置時は衛生基準を確認 |
| 受付 | 帳場・フロントの有無(施錠付き玄関と代替措置可) |
| その他 | ゴミ保管場所/洗濯物干し場/清掃用品の保管状況なども確認されることがある |
◆ 特に注意したい“自宅兼用”型の宿
「1階を宿にして、2階は自宅として使う」
「別棟だが玄関が共通」
といった構造の宿では、生活空間と営業空間の動線が混在していないかを細かく見られます。
NGとなりやすい例:
- 家族が使うトイレを宿泊者と共用
- 玄関が1つだけで、宿泊者と家族が鉢合わせする
- 宿泊スペースと生活スペースを区切る鍵がない
→ 「宿泊者の動線」と「家族の動線」が交わらないように設計することが前提です。
◆ 消防・保健所を“後回し”にすると許可は取れない
行政書士が現場でよく見るのが、以下のような事態です:
❌ ケース1:改修工事が先行してしまった
→ 消防から「再配線」「報知器追加」などの指導が入り、再工事に
→ 保健所から「受付・標識の不足」「動線の不備」を指摘される
❌ ケース2:申請後の立入検査で不合格
→ 「図面と現地が違う」「清掃不十分」「換気設備が不適」などで再検査
→ オープン予定が1ヶ月以上延期に
◆ 当事務所のサポート内容(消防・保健連携)
行政書士高見裕樹事務所では、消防・保健との調整も“事前相談段階”から同行・代理を行っています。
- 🔹 設計士・建築士と連携して、基準に適合する図面作成をサポート
- 🔹 消防署・保健所との事前相談の同席・書類作成・折衝代行
- 🔹 内装業者への基準共有・施工指示(報知器・誘導灯の配置含む)
- 🔹 検査直前のセルフチェックシート提供・現地立会いサポート
第5章|図面と設備基準
トイレ・浴室・玄関・受付の「旅館業許可に通る設計」を徹底解説!
旅館業(簡易宿所)許可の取得には、図面と現地が完全に一致していること、かつ構造・設備が基準に適合していることが前提です。
この章では、申請図面に記載すべきポイントと、それぞれの設備に求められる最低限の基準を詳しく解説します。
◆ 図面に求められる基本項目
旅館業許可申請で提出する図面は、一般的な建築図面と異なり、営業設備の配置と数値が明確であることが求められます。
🔹 必要な図面の種類(簡易宿所の場合)
| 図面名 | 必須/任意 | 内容 |
|---|---|---|
| 平面図 | 必須 | 客室、トイレ、浴室、受付、玄関などの配置(縮尺入り) |
| 求積図 | 必須 | 各室の面積(m²表記)、特に客室は正確に記載 |
| 立面図(断面図) | 任意だが推奨 | 天井高の確認、採光・換気設備の高さ関係が明確になる |
| 設備配置図 | 必須 | 火災報知器・誘導灯・消火器・手洗い場などの位置 |
| 玄関施錠図 | 条件により必要 | 帳場を設置しない場合の代替措置として必須 |
◆ トイレの基準|共同利用でも可、でも清潔性が重要
✅ ポイント
- 客室ごとに設ける必要はない(共用でOK)
- 男女共用でも可だが、十分な広さとプライバシー確保が必要
- 手洗い場の設置は必須(蛇口+洗面器)
- 便器数の目安:宿泊者10人あたり1器程度
- 洗浄便座・換気扇があると保健所の印象が良い(必須ではない)
❌ NG例
- トイレのドアが直接客室と接している
- 生活用と共用(家族が使っている)
- 洗面所とトイレの境目が不明瞭
◆ 浴室の基準|ユニットバスでもOK、給湯設備がポイント
✅ ポイント
- 客室ごとでなくてもOK(共用浴室でも可)
- ユニットバス・シャワー室でも可
- お湯が出ることが必須(給湯設備あり)
- 床材・壁材は水に強く、清掃しやすい材質であること
❌ NG例
- 湯船はあるが給湯器が壊れている
- 家族と共用で使用している
- 扉の施錠ができない(プライバシー不確保)
◆ 玄関と帳場(受付)のルール|“代替措置”が鍵
✅ 原則
簡易宿所でも「受付(帳場)」が原則必要とされています。
これは、不特定多数が出入りする施設であるため、宿泊者をチェックし、帳簿(宿泊者名簿)を備える責任者を配置する必要があるためです。
✅ 代替措置として認められる例(金沢市の場合)
| 代替措置内容 | 要件 |
|---|---|
| 玄関の施錠 | カードキー・暗証番号・インターホン等で第三者の無断出入りを防止 |
| 管理人の常駐 | 同一敷地内または近接地に管理人が滞在(緊急時対応可) |
| モニタリング設備 | カメラ設置+常時遠隔監視体制があればOKとなる場合も |
▶ 当事務所では、帳場を設置しない構造の方に「図面と写真のセット」で代替措置を提案しています。
◆ 客室の基準|採光・換気・面積の3点セットが重要
✅ 基準まとめ
| 項目 | 最低基準 |
|---|---|
| 面積 | 1人7㎡程度以上(2人部屋なら14㎡)が目安 |
| 採光 | 窓の設置が原則(※小窓・天窓は要相談) |
| 換気 | 換気扇または開閉可能な窓が必要 |
| 清掃性 | 畳・カーペットでも可だが清掃が容易であること |
❌ NG例
- ロフトや納戸を客室に転用
- 換気設備がないクローゼット型の部屋
- 面積の記載が図面と現地で異なる
◆ ゴミ置き場・清掃道具置き場・洗濯スペース
これらは細かい指摘ポイントですが、保健所によっては審査の際に確認されることがあります。
- ゴミ置き場が外から見える → 美観指導あり
- 清掃道具が共用スペースに放置 → “不衛生”と評価される
- 洗濯機を宿泊者と家族で共用 → 境界設定を求められる場合あり
▶ 図面・写真で「用途と管理区画を明確に分ける」ことで、指導を回避できます。
図面と設備基準を制す者が許可を制す!
旅館業(簡易宿所)の審査では、「図面の完成度」と「実際の設備の状態」がすべてです。
行政書士が図面チェック・施工前チェック・保健所との打ち合わせを代行することで、「一発で通る図面」と「検査に強い現場」を同時に実現することが可能です。
第6章|よくあるNGと許可が下りない事例
“ここでつまずいた”を回避!申請・設備・運営での失敗例と対策
旅館業(簡易宿所)許可の現場では、「ここさえ気をつければスムーズにいったのに…」というトラブルが多数報告されています。
この章では、許可が下りなかった・検査で不合格になった・近隣トラブルに発展したなど、実務で頻出するNG例をテーマ別に整理し、それぞれの対策も併せてご紹介します。
◆ NG①:用途地域の誤認による不許可
● ケース
「住宅街の空き家を宿にしたい」と賃貸契約したが、第一種低層住居専用地域であり、旅館業ができないと判明。
● 原因
→ 用途地域の確認をせず、物件契約を先行してしまった。
● 対策
✅ 都市計画課で用途地域証明書を取得
✅ 契約前に行政書士へ相談し、営業可能な地域かを調査する
◆ NG②:居抜き物件をそのまま使用→図面と現地が不一致
● ケース
以前ゲストハウスとして使われていた建物をそのまま使おうとしたが、実際の間取りと図面が一致せず申請不可に。
● 原因
→ 図面を流用しようとしたが、設備変更・間取り変更がされており、図面の訂正が必要だった。
● 対策
✅ 現況図面を一から作成(面積・設備・構造を正確に記載)
✅ 保健所の検査を意識して写真・配置も事前に確認
◆ NG③:消防設備の基準を満たしておらず、再工事に
● ケース
改修工事を終えてから消防に相談した結果、火災報知器の仕様が不適合でやり直しに。
● 原因
→ 施工前の消防協議を行わなかった。誤った市販品を取り付けてしまった。
● 対策
✅ 設計図が完成した段階で消防署に事前協議
✅ 認定品の火災報知器・誘導灯を指定業者に依頼する
◆ NG④:保健所検査で「生活空間との区切りが不十分」と指摘
● ケース
自宅の1階を宿にし、2階を生活スペースとしたが、玄関が共用で分離が不明瞭とされ不合格。
● 原因
→ 宿泊者と家族の動線が完全に分かれておらず、プライバシー確保・管理者の常駐確認ができない構造。
● 対策
✅ 玄関は施錠・分離し、ゾーニングを図面と写真で明示
✅ 家族用トイレや浴室と宿泊用を分ける(あるいは共用設備を営業専用に変更)
◆ NG⑤:許可取得前に予約サイトに掲載・営業開始
● ケース
「審査が通ると思っていた」ため、Airbnbや楽天トラベルに登録・予約受付を開始。
しかし検査で不備が発覚し、無許可営業扱いで是正命令+営業停止に。
● 原因
→ 「まだ営業していない」つもりでも、“予約受付”の時点で営業行為と判断される。
● 対策
✅ 許可証が交付されるまでは一切の予約受付・告知を行わない
✅ 予約サイトの登録タイミングも行政書士に相談
◆ NG⑥:近隣住民とのトラブルに発展し、住民説明のやり直しに
● ケース
簡易宿所としての許可は下りたが、騒音・ゴミ出し・出入りの多さなどを理由に住民から苦情が殺到。
● 原因
→ 開業前の説明が不十分/運営ルールがあいまい/管理体制に不安があった
● 対策
✅ 開業前に住民への簡単な説明文書・チラシを配布
✅ ゴミ出しルール・チェックイン時間・緊急連絡先などを施設内に掲示
✅ 管理者を常駐または近隣配置/連絡体制を整備
◆ NG⑦:町家物件で「景観条例」に抵触してしまった
● ケース
金沢市の町家物件を改修しようとしたが、「玄関ドア」「屋外照明」「看板のデザイン」が景観に合わないと指導。
● 原因
→ 金沢市の伝統的建造物保護地区・景観重点地区の制限を確認していなかった。
● 対策
✅ 金沢市景観政策課に事前相談
✅ 建築士・行政書士・看板業者と連携し、看板・照明・外観も含めて事前設計
▶ グレーゾーン=要注意!「多分大丈夫」は最も危険
旅館業(簡易宿所)の許可において、**「おそらく大丈夫だろう」**という判断で進めると、
ほぼ確実に“補正”や“指導”が入り、営業開始が1〜2か月遅れるリスクがあります。
行政書士の役割は、「グレーゾーンを白黒はっきりさせること」。
当事務所では、疑義がある場合は必ず関係機関(保健所・消防・都市計画課)に事前照会し、安全ルートで進める方針です。
第7章|行政書士高見裕樹事務所のサポート体制
物件選び・設計・改修・申請まで “本気で宿を始めたい人”のための完全支援
簡易宿所の許可取得や民泊事業の立ち上げにあたっては、
行政手続きだけではなく、物件の確保や内装の改修、図面作成、消防調整など多くのステップが絡みます。
「何から手をつけたらいいかわからない」
「それぞれ別の業者に頼んでいたら時間もコストもかかる」
そう感じたことはありませんか?
私たち行政書士高見裕樹事務所では、**“開業したい”の想いを形にするための“丸ごとサポート体制”**を整えています。
◆ ステップ①|【物件選びからスタート】
▶ 適法に営業できる立地・構造かを「プロ目線」でチェック
宿泊施設に使用できる物件は、「どこでもいい」わけではありません。
都市計画法による用途地域の制限、建築基準法上の構造要件、消防法への適合性…。
高見事務所では、提携不動産会社「ふちどり不動産」と連携し、
“用途地域の確認”や“営業可能性”を事前に調査したうえで、開業に適した物件をご紹介します。
✅ 住宅地だけど用途変更で営業可能?
✅ 古民家でも簡易宿所として使える?
✅ 市街化調整区域はNG?
こうした疑問に対して、契約前にしっかり調査し、判断材料を提供します。
◆ ステップ②|【改修・リフォームも自社で対応】
▶ 「許可の下りる工事」を熟知した施工業者が内装を手がけます
宿泊施設には、「トイレ・浴室の数」「客室の面積」「窓の採光・換気」「受付の見通し」など、細かい構造基準があります。
一般的なリフォーム会社に依頼しても、**“保健所が求める基準を知らない”**まま工事が進んでしまい、
申請後に“やり直し”になる事例も後を絶ちません。
行政書士高見裕樹事務所では、自社運営のリフォーム会社(株式会社Kプランニング)を通じて、
旅館業許可に必要な構造・設備を把握した上での改修工事が可能です。
✅ 受付の見通しを確保するパーテーション設置
✅ 消防法に適合した避難経路や誘導灯の配置
✅ 町家物件に合わせた外観規制への配慮(景観条例対応)
すべてを把握したチームが対応します。
◆ ステップ③|【図面・手続き・立入検査まですべて代行】
▶ 面倒な行政書類も“まるごと任せてOK”
旅館業許可の申請において必要となる書類は、多岐にわたります。
- 構造設備の概要書
- 敷地周辺の見取図
- 配置図
- 平面図(寸法入り)
- 営業計画書
- 管理体制の説明資料
- 消防設備の一覧
- 使用承諾書(賃貸の場合)
これらをすべてご自身で用意するのは、かなりの労力がかかります。
当事務所では、書類の作成・関係機関との調整・立入検査の立会いまで、すべて対応いたします。
さらに、金沢市など条例の厳しい自治体でも、
都市計画課・建築指導課・消防署などとの協議を事前に行い、最短ルートでの許可取得を実現します。
◆ ステップ④|【開業後の運営支援も可能】
▶ 届出・変更・相続・法人化…長期的なパートナーとして
許可取得後も、さまざまな対応が必要となります。
- 営業者変更(法人化など)
- 相続に伴う名義変更
- 増築・間取り変更に伴う構造変更届
- 簡易宿所から旅館営業への種別変更
- 売却や賃貸に伴う手続き
当事務所では、**「許可を取って終わり」ではなく、「開業後も支え続ける」**体制を整えています。
長期的な事業パートナーとして、安心して経営に専念できる仕組みを提供しています。
▶ 一括サポートのメリット
| 項目 | 通常の流れ(複数業者) | 高見事務所なら |
|---|---|---|
| 物件調査 | 不動産業者に確認/別途行政相談 | 最初から営業可否を調査 |
| リフォーム工事 | 通常の業者/後からNGの可能性 | 許可基準に適合した設計 |
| 申請手続き | 書類を自分で準備、役所に何度も出向く | すべて丸投げ可能 |
| 開業後の相談 | 自力で対応 | 長期的なパートナー対応 |
第8章|まとめ
「宿を始めたい」は最初の一歩で9割決まる
ここまで、旅館業法に基づく「簡易宿所」の開業について、
物件選びから構造要件、消防・保健所対応、申請手続き、そして実際のサポート体制に至るまで、幅広く解説してきました。
改めて強調したいのは――
「簡易宿所を始める」=「許可を取れば終わり」ではないということです。
◆ 宿を始めるためには“多面的な視点”が必要
- そもそもその場所で宿ができるのか?(都市計画法・条例)
- 建物は基準を満たしているか?(建築基準法・消防法・旅館業法)
- 客室の数や間取り、受付の位置は適切か?(図面・構造)
- 管理体制は十分か?(管理人常駐・緊急連絡体制)
- 書類作成や役所調整に耐えうるか?(手続き負担)
…これらすべてにYESと答えられたとき、
はじめて「合法的に、継続的に、収益を生む宿泊事業」がスタートできます。
◆「早く動いた人」が、結果を出している
当事務所にご相談いただいた方の中には、
- ✅ 築50年の町家を旅館にリノベして、観光客から大人気に
- ✅ 自宅の一部を使って副収入を得る“家族経営型”宿を開業
- ✅ 空き家を活用して地域の活性化に取り組む自治体支援型民泊
など、さまざまな形で宿泊事業を成功させている方がいらっしゃいます。
そして、どの方にも共通していたのは――
「許可取得や改修計画を最初にしっかり固めた」ことです。
◆「思い立った今」が、一番早いスタート地点
「いつか民泊を始めたい」
「空き家をどうにかしたい」
「副業で宿をやってみたい」
そう思っている間に、
物件は売れ、制度は変わり、ライバルは増えていきます。
だからこそ、最初の一歩を、今日踏み出してみてください。
それが「あなたの宿」の始まりです。
▶ ご相談はこちらから
行政書士高見裕樹事務所では、
「物件選び」から「許可取得・改修工事」までをワンストップでサポートしています。
- ✅ 無料の開業可否診断
- ✅ 用途地域・条例の調査
- ✅ 図面作成や保健所・消防協議の代行
- ✅ 施工業者との調整
- ✅ 営業許可取得まで一括支援
まずはお気軽にお問い合わせください。
📞 電話:076-203-9314
🖥 問い合わせフォーム:行政書士高見裕樹事務所「お問い合わせページ」から
👉 https://takami-office.net/contact/