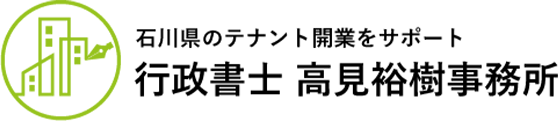行政書士に遺言書作成を相談するメリット
遺言書は「財産の分け方」だけでなく、「誰に何をどう託すか」を明確にする大切な意思表示です。インターネットの情報だけで自作することも可能ですが、文言の曖昧さや形式の不備で無効になったり、相続人間の解釈違いを生むことがあります。行政書士に相談すれば、法律の形式要件に沿った文案作成や、家族構成・財産状況に合わせた条項整理ができ、将来のトラブルを未然に防ぎやすくなります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
自筆証書遺言は手軽で費用を抑えられる一方、要件不備や紛失リスクが課題です。法務局の遺言書保管制度を使えば原本保管と検認不要のメリットがあります。公正証書遺言は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・変造リスクが低く、家庭裁判所の検認も不要です。どちらを選ぶかは、財産の複雑さやご家族の状況、確実性へのニーズで判断します。
行政書士ができること・できないこと
行政書士は遺言内容の設計、財産・相続人の整理、推敲・文案作成、必要書類の収集支援、公証役場との連携などを行います。一方、紛争性が強い場合の交渉や訴訟代理は弁護士の領域です。税務最適化の詳細設計は税理士に相談します。必要に応じて専門士業と連携してもらえるか、事前に確認すると安心です。
作成までの基本フロー
まずは「財産目録」と「家族関係図」を簡単で良いので作ります。現金・預貯金・不動産・有価証券・事業資産・デジタル資産・負債など、漏れを防ぐ意識が大切です。そのうえで分け方の方針と、付言事項(家族へのメッセージや遺言の背景)をまとめます。
1. 事前準備で揃えるもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・戸籍関係書類(必要に応じて)
・不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書
・金融資産の残高が分かる資料
・保険証券、貸付契約、借入明細など債権債務の資料
・預金口座や各サービスの名義表記の確認メモ
2. 行政書士とのヒアリング
現状の悩み、相続人同士の関係性、事業承継の意向、特定の財産に対する希望などを整理します。争いの芽になりやすい論点(不動産の共有、特定の子への偏り、遺留分への配慮)を洗い出し、代替案も検討します。
3. 文案作成と推敲、公証役場の予約
自筆証書なら自書や加除訂正のルール、日付・署名・押印の方法、目録の扱いを確認します。公正証書の場合は必要書類を整え、証人の手配、公証役場との日程調整を進めます。オンラインでの事前打ち合わせに対応する役場もあるため、スケジュールが取りやすくなっています。
よくある失敗と回避策
遺言は有効でも、実務で困るケースがあります。以下は代表例です。
財産・相続人の把握漏れ
ネット証券、仮想通貨、マイルやポイント、サブスクの家族アカウントなど、見落としがちな資産・契約を洗い出しましょう。相続開始後の探索は手間が増え、トラブルの火種になります。定期的な資産リスト更新を習慣化すると安心です。
表現の曖昧さと形式不備
「できれば」「なるべく」など曖昧な表現は解釈の余地を生みます。誰に、何を、どの割合で、代替不能な場合の予備指定はどうするのかまで具体化します。自筆証書では、日付・署名・押印、加除訂正の方法、ページ綴り、目録の作り方に注意します。
保管と見直しを怠る
作って終わりではなく、保管場所とアクセス方法を家族や受遺者が把握しているか確認します。ライフイベント(結婚・離婚・出生・転居・大きな資産変動)のたびに見直すと、内容の陳腐化を防げます。
費用感と期間の目安
費用は依頼内容や地域で幅があります。目安としては、ヒアリング・設計・文案作成・書類収集支援・公証役場調整まで含むと一定の費用が想定されます。期間は、資料が揃ってから自筆証書でおおむね1~2週間、公正証書で2~4週間程度が一つの目安です。複雑な財産や関係者調整が必要な場合は時間を見込みましょう。
まとめ:将来の安心を今から整える
遺言書は「今の思い」を未来へ確実に届ける仕組みです。行政書士に相談することで、形式の落とし穴を避け、あなたの意思を実務で実現しやすい形に整えられます。まずは財産と家族の現状を書き出し、相談の第一歩を踏み出してみてください。