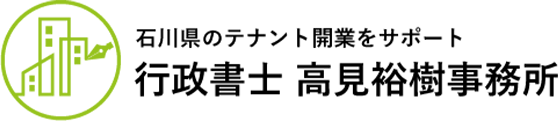🏗 “軽微工事でも安心を”|リフォーム会社が建設業許可を取るべき理由
はじめに
「うちは小規模だから建設業許可はいらない」
「500万円以下なら関係ないと聞いた」
──こう考えているリフォーム会社は少なくありません。
確かに、法律上「軽微な工事」は建設業許可が不要です。しかし実務の現場では、許可を持っているかどうかで信頼度・単価・仕事の幅が大きく変わるのが現実です。
この記事では、石川県で実際にリフォーム事業を展開している方に向けて、建設業許可を取得するメリットと実務的なポイントを詳しく解説します。
リフォーム専門会社としての信頼を高め、元請案件を増やすための「次の一手」として、ぜひ参考にしてください。
1. 建設業許可がいらない「軽微工事」とは?
まず、建設業法上の「軽微工事」の定義を整理しておきましょう。
建設業許可が不要な工事とは、次のいずれかに該当するものです。
- 工事一件の請負代金が500万円未満(消費税を除く) の工事
- 建築一式工事の場合は1,500万円未満(または延べ面積150㎡未満の木造住宅)
たとえば「キッチンリフォームで200万円」「内装張替えで100万円」といった案件は、一般的に許可不要です。
しかし注意すべきは、“材料費を含めた総額”で判断されること。
工事費だけで500万円未満に抑えても、材料費込みで超えると「許可が必要」となります。
また、同じ現場で複数契約に分けて請ける「分割見積」も、法的には一連の工事とみなされるケースがあります。
石川県内でも、こうした見積方法が原因で「無許可営業」に該当すると指導を受ける事例があります。
2. 許可を取ることで広がる3つのメリット
① 見積単価のアップ
建設業許可を持つと、発注者側(個人・法人問わず)からの信頼が格段に上がります。
許可=「一定の経営経験・技術・財務基盤を持つ事業者」
と評価されるため、単価を“値切られにくく”なります。
同じ内容の見積書でも、無許可業者より10〜15%高くても受注できるケースは少なくありません。
② 元請案件の獲得
多くの法人・不動産管理会社・ゼネコンでは、許可業者以外との取引を禁止しています。
そのため、下請中心だったリフォーム業者でも、許可取得を機に元請として工事を請けられるようになります。
公共工事や大手企業との取引、マンション改修・店舗リノベーションなど、受注の幅が一気に広がります。
③ トラブル時の信頼確保
施工後にクレームや不具合が発生した場合も、「許可業者である」というだけで信頼感が違います。
許可証を掲示できる業者は、発注者にとって安心材料。
特に住宅リフォームでは「業者選び=信頼性」が大きな決め手です。
3. 許可取得後の“変化”──実例紹介
【事例①】金沢市内の内装業A社
長年、アパートの小規模リフォームを中心に活動していたA社。
建設業許可を取得後、500万円を超えるリノベーション案件を直接請け負えるようになりました。
下請から元請へシフトし、売上は2年で約1.8倍に。
【事例②】白山市のリフォーム会社B社
法人化と同時に建設業許可を取得。
「許可を持っている」というだけで、地元の管理会社やオーナーからの信頼が増し、見積依頼が急増。
今では年間の契約件数の半数以上が元請案件となっています。
【事例③】工務店との協業がスムーズに
工務店からの依頼で内装・水回りの下請を行っていたC社は、許可を取得したことで、元請工務店と対等な立場で契約を結べるようになりました。
契約書作成や請負金額の調整もスムーズになり、経営の安定につながっています。
4. 石川県で建設業許可を取るための基本要件
石川県で許可を取得するには、以下4つの条件を満たす必要があります。
1️⃣ 経営業務管理責任者がいること
→ 5年以上の建設業経営経験、または一定の役職経験が必要。
2️⃣ 専任技術者がいること
→ 有資格者(建築士・施工管理技士など)または10年以上の実務経験。
3️⃣ 財産的基礎(500万円以上の資金力)
→ 残高証明や決算書などで証明します。
4️⃣ 欠格要件に該当しないこと
→ 暴力団関係や破産未免責などがないこと。
💡 ポイント:法人化と同時申請も可能!
これから法人化を検討している方は、会社設立と建設業許可申請を同時に行うことでスムーズに進められます。
行政書士高見裕樹事務所では、法人設立+建設業許可の同時申請にも対応しています。
5. リフォーム業に多い業種区分
リフォーム工事の内容によって、申請すべき「業種」が異なります。
| 工事内容 | 該当する業種 |
|---|---|
| 内装・クロス・床 | 内装仕上工事業 |
| トイレ・キッチン・配管 | 管工事業 |
| 外壁塗装・屋根塗装 | 塗装工事業 |
| 防水施工 | 防水工事業 |
| カーポート・フェンス・エクステリア | 建具工事/鋼構造物工事/とび・土工工事 |
| 住宅リノベーション全般 | 建築一式工事業 |
多くのリフォーム会社は「内装仕上工事業」「建築一式工事業」「管工事業」を組み合わせて取得しています。
まずは主力業務に合わせて1業種からスタートするのが現実的です。
6. 許可取得の流れと期間
1️⃣ 事前ヒアリング・要件確認(約1週間)
→ 実務経験・資格・決算内容を確認。
2️⃣ 書類準備(2〜3週間)
→ 経営経験証明書、登記簿謄本、残高証明書など。
3️⃣ 石川県庁へ申請
→ 書類一式を行政庁に提出。
4️⃣ 審査期間(約30〜45日)
→ 補正対応などを経て許可証交付。
5️⃣ 許可証交付後、名刺・HPに許可番号を掲載可能
7. 許可取得後の維持・管理
建設業許可は「取りっぱなし」ではありません。
維持のためには定期的な手続きが必要です。
- 毎年:「事業年度終了報告書(決算変更届)」の提出
- 5年ごと:「更新申請」
- 経営業務管理責任者や技術者が変わったとき:「変更届」
これらを怠ると、更新ができなくなったり、再申請が必要になる場合があります。
行政書士高見裕樹事務所では、取得後の維持管理も一括でサポートしています。
8. 自社施工+許可で“最強の信頼”を
リフォーム会社にとって、建設業許可は「ブランド」でもあります。
許可を持つことで、
- 工務店やハウスメーカーとの取引拡大
- 銀行融資・リース契約の信用向上
- 新規顧客への営業時の信頼強化
など、経営基盤の安定化につながります。
さらに、行政書士高見裕樹事務所では自社グループ「株式会社Kプランニング」を通じて、
リフォーム・改装工事を自社施工できます。
「申請」だけでなく、「実際の工事体制づくり」まで一気通貫で支援できる点が最大の強みです。
9. 行政書士に依頼するメリット
建設業許可の申請は、
- 経営業務管理責任者の証明(在職証明書・確定申告書など)
- 技術者の実務経験証明
- 財務基礎の証明書類作成
など、一般の方が独力で行うには非常に複雑です。
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 必要書類の収集サポート
✅ 経験・実務の整理と証明方法の提案
✅ 書類作成・代理提出
✅ 許可後の届出・更新管理
までをすべて代行いたします。
10. まとめ
リフォーム業における建設業許可は「任意」ではなく、次のステージへ進むための投資です。
- 見積単価を上げたい
- 元請として仕事を増やしたい
- 法的にも安心できる会社にしたい
そんな方こそ、今が申請のチャンス。
石川県内での申請は、経験豊富な**行政書士高見裕樹事務所(076-203-9314)**へご相談ください。
法人化、資金調達、リフォーム施工までワンストップで支援いたします。
📩 お問い合わせはこちらから
行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/