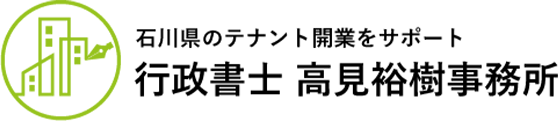「相続人にどう伝える?」
残置物の通知書を行政書士が作成する理由と実務対応
不動産を所有していると、入居者が退去した後や所有者の死亡に伴い、室内に荷物が残されたままになることがあります。
古い家具、家電、衣類、生活用品など、**いわゆる「残置物」**と呼ばれるものです。
この残置物、勝手に処分してはいけないことをご存じでしょうか。
特に、借主が亡くなっている場合や、所有者が相続により変わる場合は、残置物の所有権が相続人に移っているため、慎重な対応が求められます。
行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)では、こうした残置物の扱いに関して、相続人への通知書作成業務を多数手がけています。
本記事では、大家さん・不動産オーナー様が知っておくべき法的リスクと、正しい対応手順について、実務の視点から詳しく解説します。
1.残置物とは?大家さんにとっての“見えないリスク”
「残置物」とは、退去や相続などの事情で、建物内に置き去りにされた動産(家具・家電・日用品など)を指します。
賃貸物件の場合、入居者の所有物であるため、契約終了後であっても勝手に処分すると違法行為になる可能性があります。
特に相続が関わる場合、相続人が「遺品を勝手に処分された」と主張すれば、損害賠償請求を受けるおそれもあります。
たとえば——
- 借主が亡くなり、親族が現れず放置状態
- 相続人が複数いて、誰が荷物を引き取るか決まらない
- 明け渡し訴訟で勝訴したものの、荷物が残っている
このようなケースでは、単に「捨ててしまう」ことが最も危険です。
2.相続人への「通知」が必要な理由
民法上、相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産はすべて相続人に引き継がれます(民法第896条)。
つまり、部屋に残された荷物は**相続人の財産(遺産)**です。
そのため、残置物を処分するには、
- 相続人が引き取る、
- 相続人が放棄する、
- 相続人が処分を承諾する、
いずれかの意思確認を行う必要があります。
この「意思確認」を文書で行うのが、**行政書士が作成する『残置物通知書』**です。
3.残置物通知書とは?内容と目的
残置物通知書とは、大家さん(または管理会社)が、残された荷物の所有者または相続人に対して、
「この荷物をどのように扱うか指示を求める」ための正式な文書です。
通知書の目的は、
- 所有者の意思を確認する
- 引取り・放棄・処分の選択を促す
- 期限を設定し、対応がない場合の取扱いを明示する
ことにあります。
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような形式で作成しています。
【残置物通知書に記載する主な内容】
- 物件の所在地と残置物の概要
- 処分予定日や保管期限
- 相続人に求める対応(引取・放棄・処分承諾など)
- 回答期限・連絡先
- 期限内に返答がない場合の対応方針(例:廃棄処分)
通知書を内容証明郵便で送ることで、
「いつ・誰に・どんな内容を通知したか」という証拠が残り、
後日の紛争を防ぐことができます。
4.通知の前に必要な相続人調査
通知を出すには、誰が相続人なのかを特定することが不可欠です。
行政書士高見裕樹事務所では、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などを取得し、
相続関係説明図を作成することで、相続人を確定します。
相続人が複数いる場合には、代表相続人宛に通知を送るか、
または全員に個別送付するケースもあります。
「誰に送ればよいか分からない」「相続人が県外に住んでいる」など、
不明確な場合も行政書士が代理で調査を行い、通知先を確定させます。
5.通知後の流れ:相続人の反応と対応パターン
通知書を送付した後、相続人からは主に3つの反応があります。
① 荷物を引き取る意思を示す場合
相続人自身で引取り日程を調整し、残置物を搬出します。
この場合、処分費用は原則として相続人負担となります。
② 放棄・処分を承諾する場合
行政書士が作成した**「残置物所有権放棄書」や「処分承諾書」**に署名・押印をもらい、
法的リスクなく残置物を処分できます。
③ 連絡が取れない・回答がない場合
一定期間(通常2〜4週間)経過しても反応がない場合は、
通知書に記載した「期限までにご連絡がない場合は廃棄処分します」の文言に基づき、
処分手続へ移行します。
この対応記録を残しておくことが非常に重要です。
6.トラブル事例と行政書士による解決
ケース1:親族が揉めて処分が進まない
兄弟間で「思い出の品だから処分したくない」「遠方で取りに行けない」と意見が分かれることもあります。
行政書士が間に入り、書面で整理することで、合意形成がスムーズになります。
ケース2:相続人が不明・音信不通
戸籍調査により相続人を特定し、公示送達に準じた対応で通知を行います。
これにより、後日「知らされていない」と主張されるリスクを防止できます。
ケース3:賃貸契約者が生前に残した荷物の処分
生前に「残置物放棄特約」を設けていない場合でも、
相続人とのやり取りを丁寧に記録することで、安全に整理が可能です。
7.行政書士に依頼するメリット
✅ 1.法的根拠を踏まえた文書作成
通知書・放棄書・確認書など、全て法的要件を満たした形で作成します。
✅ 2.相続人調査から一括対応
戸籍調査・通知先特定・内容証明の発送までをワンストップで対応します。
✅ 3.不動産と許認可の専門性
行政書士高見裕樹事務所は、不動産 × 許認可 × リフォームを一貫して行うため、
残置物処理後の売却・再賃貸・活用まで見据えたサポートが可能です。
8.残置物処理後のステップ:再活用までの流れ
残置物を整理した後は、物件を再活用できる状態に戻すことが重要です。
- 室内の原状回復(清掃・修繕・撤去工事)
- 建物・土地の再活用(再賃貸・売却・リフォーム)
- 所有権・登記情報の整理(司法書士と連携)
当事務所では、グループ会社の**ふちどり不動産(TEL:076-203-6605)**や
**株式会社Kプランニング(リフォーム・解体担当)**と連携し、
残置物の処理後も「すぐに次の活用へ」進める体制を整えています。
9.実務対応の費用目安
※案件内容・相続人数・調査範囲により変動します。
| 業務内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 相続人調査(戸籍収集) | 33,000円~ |
| 残置物通知書作成 | 33,000円~ |
| 内容証明郵便発送(1通) | 5,000円程度+郵送料 |
| 残置物所有権放棄書作成 | 22,000円~ |
| 処分承諾書作成・同意取得 | 22,000円~ |
※複数相続人への対応・現地確認が必要な場合は別途見積もり。
10.「来るもの拒まず」——大家さんの“最後の砦”として
残置物の問題は、「相続」「契約」「現場管理」の3つが絡む厄介な案件です。
しかし、適切な手順を踏めば、法的リスクを回避しながら円満に整理できます。
行政書士高見裕樹事務所では、
どんなやっかいな案件でも「来るもの拒まず」の姿勢で、
大家さん一人ひとりに寄り添いながら、確実に解決へ導きます。
📞 ご相談はこちら
行政書士高見裕樹事務所
不動産 × 許認可のスペシャリストが、あなたの課題を解決します。
📍所在地:石川県金沢市
📞 電話:076-203-9314
✉️ お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
👉 どんな小さなご相談でも大丈夫です。
残置物の通知・相続人への連絡・処分書類の整備など、
お困りの際はお気軽にご相談ください。