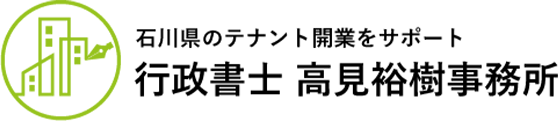相続人調査・相続関係説明図・法定相続情報の作成|相続手続きの第一歩を徹底解説
はじめに
相続手続きを始めるとき、最初に必要となるのが「相続人は誰か」を確定する作業です。
「相続人が多い」「戸籍が遠方にある」「誰が相続人になるのか分からない」――そんな場面では、相続人調査・相続関係説明図・法定相続情報の作成が出発点となります。
本記事では、それぞれの意味と作成の流れ、実務上の注意点を解説します。
相続人調査とは?
相続人調査とは、被相続人(亡くなった方)の戸籍を出生から死亡まで収集し、法律上の相続人を確定する作業です。
なぜ必要?
- 相続登記や預金解約、遺産分割協議には相続人全員の署名・押印が必須
- 一人でも漏れると無効となり、手続きがやり直しになる
- 相続人に認知や養子縁組などの「隠れた相続人」がいる場合もある
👉 戸籍の収集は数十通に及ぶことも珍しくなく、専門知識がないと見落としが発生しやすいのが実務です。
相続関係説明図とは?
相続人調査で確定した相続人を、系図形式でまとめた図のことです。
戸籍の束を提出する代わりに、この説明図1枚で済ませられるケースが多くあります。
特徴
- 家系図のように分かりやすく相続人を一覧化
- 法務局や金融機関で「戸籍に代わる証明」として利用可能
- 自由形式であるが、戸籍の内容と一致していることが絶対条件
👉 行政書士が作成することで、戸籍との整合性を担保し、誤記や漏れを防ぐことができます。
法定相続情報一覧図とは?
2017年に始まった制度で、法務局に戸籍一式と相続関係説明図を提出すると、**「法定相続情報一覧図の写し」**を無料で交付してもらえます。
メリット
- 登記、銀行、証券会社など、複数の相続手続きに同じ一覧図を使い回し可能
- 戸籍の束を何度も提出する必要がなくなる
- 無料で何通でも交付可能
👉 相続手続きを効率化する強力なツールであり、当事務所でも積極的に活用をおすすめしています。
実務上の注意点
- 戸籍の収集は「本籍地の市区町村役場」ごとに請求 → 郵送請求も可
- 相続人が全国に散らばっている場合、1か月以上かかることも
- 相続人に未成年・行方不明者がいる場合は、別途家庭裁判所の手続きが必要
- 法定相続情報の作成は登記官のチェックが入るため、正確性が必須
行政書士に依頼するメリット
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく収集
- 複雑な家族関係でも正確な相続関係説明図を作成
- 法定相続情報の申出を代行し、複数通の写しを取得
- 相続登記を担当する司法書士や不動産売却を扱う不動産会社と連携し、相続全体をワンストップ対応
👉 当事務所は「相続×不動産売却」「相続×残置物処理」まで見据えた実務対応が強みです。
まとめ
- 相続人調査 → 相続人を戸籍で確定
- 相続関係説明図 → 相続人関係を図式化
- 法定相続情報 → 手続きを簡素化できる一覧図
この流れを正しく踏むことで、相続手続きがスムーズに進みます。
「誰が相続人なのか分からない」「戸籍をどう集めればよいか不安」という方は、まずはご相談ください。
👉 行政書士高見裕樹事務所では、相続人調査から相続関係説明図・法定相続情報の作成まで一括サポートしています。
お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/