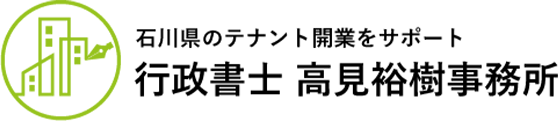第1章|宅建業免許ってそもそも何?
仲介・買取・管理との関係性を解説!
「不動産業を始めたいけど、何が必要なのか分からない」
「宅建業免許って“宅建士の資格”とは違うの?」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、まずは宅建業免許の基本からご説明します。
■ 宅建業免許とは?
宅建業免許とは、不動産の「売買」や「賃貸」の仲介・代理を業として行う場合に必要な免許です。
この免許は、**宅地建物取引業法(通称:宅建業法)**に基づいており、「不動産業を営む=免許が必要」と理解して問題ありません。
宅建士(=個人の国家資格)とは異なり、宅建業免許は法人または個人事業者に対して発行される営業許可です。つまり、資格だけを持っていても、会社として宅建業を行うには別途“免許取得”が必要です。
■ 宅建業に該当する代表的な業務
| 業務内容 | 宅建業免許の要否 |
|---|---|
| 不動産の売買の「仲介」 | 必要 ✅ |
| 不動産の「買取・転売」 | 必要 ✅ |
| 不動産の「賃貸仲介」 | 必要 ✅ |
| 賃貸物件の「管理」 | 不要 ❌(※例外あり) |
| 自社保有物件の「貸付」 | 不要 ❌ |
たとえば、自社物件を貸すだけの「オーナー業」は宅建業に該当しません。
しかし、他人の物件を「紹介」したり「間に入って契約を成立させる」場合には、“反復継続して行う”限り免許が必須となります。
■ “宅建業者”であるメリットとは?
宅建業免許を取得すると、
- ✅ 営業所を設けて堂々と「不動産業」を名乗れる
- ✅ レインズ(不動産流通標準システム)への登録が可能
- ✅ 仲介手数料などのビジネスモデルを構築できる
- ✅ 顧客やオーナーとの信用性が高まる
など、不動産業としての土台が一気に整います。
副業や小規模からでもスタートできる宅建業ですが、免許の取得は“はじめの一歩”にして最大の関門でもあります。
第2章|免許が必要なケース・不要なケース
どこからが“宅建業”?その境界線を明確に
不動産に関する業務は多岐にわたりますが、すべての業務に宅建業免許が必要なわけではありません。
ここでは、「宅建業に該当する業務/しない業務」の判断基準をわかりやすく解説します。
■ 宅建業法上の「宅建業」とは?
宅地建物取引業法における「宅建業」の定義は、以下のいずれかを**“反復継続して”**行うことです。
- 宅地または建物の 売買・交換・賃貸 の 代理または媒介(仲介) をする
- 自ら宅地または建物を 売買または交換 する(いわゆる「買取再販」)
これらに該当する場合、原則として宅建業免許が必要になります。
■ 実例で見る「必要なケース」と「不要なケース」
| ケース | 宅建業免許の必要性 | 理由 |
|---|---|---|
| A社が月に数件、不動産売買の仲介を行っている | 必要 ✅ | 反復継続した媒介業務 |
| Bさんが相続した不動産を1回だけ売却 | 不要 ❌ | 営利性・反復性がない |
| C社が自社保有のアパートを賃貸 | 不要 ❌ | 自社所有の物件を貸すだけ |
| D社がオーナー物件の入居者募集を仲介 | 必要 ✅ | 他人の物件の媒介業務 |
| E社が古家を買取・リフォーム後に再販 | 必要 ✅ | 自ら売主となる反復取引 |
| Fさんが知人の物件を1回だけ紹介 | 不要 ❌(原則) | 無償・単発・個人的な行為なら不要 |
| G社が賃貸物件の管理(家賃集金など) | 不要(※)❌ | 管理業務のみでは対象外 ※例外あり |
■ 注意したい“グレーゾーン”の判断基準
次のようなケースは、免許が必要になる可能性があるため注意が必要です。
- ✅ 副業や兼業で不動産を紹介している
→「本業じゃないから大丈夫」と思っていても、継続して紹介料を得ている場合は免許が必要になります。 - ✅ 管理業務の一環で入居者募集もしている
→管理業務だけなら不要ですが、オーナーの代わりに入居者の募集を行って契約を締結する場合は宅建業に該当します。 - ✅ 自社保有物件以外も取り扱っている
→「自社名義じゃない不動産を扱う」=宅建業にあたる可能性が高くなります。
■ 迷ったら「要件確認」だけでもOK!
「うちの事業って宅建業になる?」という段階でご相談いただく方も多くいらっしゃいます。
行政書士としての立場から、許認可が必要なライン・不要な範囲を丁寧にご説明し、今後の事業展開に合わせた対応方針のご提案も可能です。
次章では、実際に石川県で宅建業免許を取得する際の申請窓口や申請フローを詳しくご案内します。
第3章|石川県での申請先とフロー
県庁?市役所?本店所在地で変わる提出先
宅建業免許は全国共通の制度ですが、申請窓口は「事業所の所在地」によって異なることをご存じでしょうか?
ここでは、石川県内での免許申請における「提出先」と「具体的な流れ」について、わかりやすく解説します。
■ 「知事免許」と「大臣免許」の違いとは?
宅建業免許には、大きく分けて以下の2種類があります。
| 種類 | 対象 | 提出先 |
|---|---|---|
| 知事免許 | 営業所が1つの都道府県内にある場合 | 各都道府県の担当課(例:石川県庁) |
| 大臣免許 | 営業所が複数都道府県にまたがる場合 | 国土交通大臣(実務は各地方整備局) |
例えば、石川県金沢市だけで営業する場合は「石川県知事免許」となり、石川県庁の土木部建築住宅課などが窓口になります。
■ 石川県内の申請窓口と担当部署
| 地域 | 提出先 | 備考 |
|---|---|---|
| 金沢市・野々市市・白山市・能美市など | 石川県庁(土木部建築住宅課) | 金沢駅から車で約10分/要事前予約がベター |
| 七尾市・輪島市など(能登エリア) | 各県庁出張所や窓口で相談後、本庁へ提出 | 実質的には本庁一括処理が多い |
| 複数県にまたがる営業所(例:石川+富山) | 北陸地方整備局(大臣免許) | 高度な書類・法人体制が求められる |
※申請書類の一部は、地元市役所(商業登記簿や住民票取得)などからの取得が必要になるケースもあります。
■ 石川県での免許申請の基本フロー(知事免許)
- 事前相談・確認(行政書士や担当部署)
- 必要書類の収集・作成
- 提出先への申請書提出
- 審査期間(約30~40日)
- 免許証の交付・宅建業者票などの整備
- 事務所の準備・営業開始(標識・専任宅建士の配置など)
■ 金沢市内の不動産業者様へ:当事務所のサポート例
行政書士高見裕樹事務所では、金沢市・野々市市・白山市など、石川県内の知事免許取得に多数の実績があります。
✅ 法人設立と同時に宅建業免許を取得
✅ 賃貸仲介業スタートに向けた事務所確認・写真撮影サポート
✅ 開業後の標識掲示、業務帳簿の整備サポート
など、“免許を取るだけ”で終わらない実践的なサポートを提供しています。
第4章|免許取得の5大要件
「宅建士がいればOK」じゃない理由
宅建業免許は、単に宅地建物取引士(宅建士)の資格者がいれば取れるわけではありません。
免許取得のためには、法律で定められた5つの要件をすべて満たす必要があります。
この章では、宅建業免許の「基本要件」と注意点をわかりやすく解説します。
■ 要件①:事務所要件(営業所の確保)
宅建業を営むには、**「独立した事務所」**が必要です。
✅ 他業種と明確に区分されていること(例:美容室の一角は不可)
✅ 外から「宅建業を営んでいる」とわかる看板や表札があること
✅ 専任の宅建士が常勤できる物理的なスペースがあること
「とりあえず自宅でスタート」したいという方も多いのですが、
自宅兼事務所の場合は“事務所部分が独立している”ことが必須条件です。
間取りや使用実態によっては不許可になることもあるため、注意が必要です。
■ 要件②:人的要件(専任の宅建士)
営業所ごとに、専任の宅建士を1名以上置くことが義務付けられています。
ここでの「専任」とは、その事務所に常勤し、宅建業務に専従していることを意味します。
✅ 他の会社との兼務NG
✅ 学校に通っている学生不可
✅ 週3回勤務などの非常勤も不可
たとえば代表者が宅建士であっても、他社の代表も兼ねている場合は「専任」と認められない可能性があります。
これはよくある「不許可パターン」なのでご注意ください。
■ 要件③:欠格事由に該当しないこと
宅建業免許は、下記のような「欠格事由」に該当すると取得できません。
✅ 過去5年以内に宅建業法違反などで処分歴がある
✅ 成年被後見人、破産者で復権していない
✅ 暴力団関係者やその関係法人
✅ 刑罰(禁錮以上)を受けた者 など
※役員や主要出資者も含めて審査対象になるため、法人役員全員の経歴書類の提出が必要です。
■ 要件④:財産的要件(営業保証金 or 弁済業務保証金)
宅建業を営むには、顧客を保護するための「営業保証金」または「弁済業務保証金分担金」の供託が義務です。
| 選択肢 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 営業保証金 | 法務局に供託 | 1,000万円(本店) | 原則制度/資金負担大 |
| 弁済業務保証金分担金 | 宅建協会に加入し支払 | 60万円(本店) | 協会加入が前提 |
中小事業者の多くは、宅建協会(全宅・全日など)に加盟して60万円を支払うパターンが主流です。
■ 要件⑤:誠実性の確保(業務遂行能力)
最後に、「業務を誠実に遂行できる体制があるか」も審査されます。
✅ 業務経験がある、または宅建士としての実務経験がある
✅ 業務遂行に必要な人員・体制がある
✅ 不動産業としての具体的な事業計画や説明責任を果たせる体制である
「実績ゼロでもOK」ではあるものの、免許後の帳簿作成・重要事項説明・契約書の交付などの運用ができる体制かどうかが重視されます。
■ 当事務所では、要件確認も無料対応!
行政書士高見裕樹事務所では、宅建業免許取得を目指す方へ、事前の「要件チェック」や「事務所写真の撮影指導」などを無料で実施中です。
特に「自宅で始めたい」「法人設立と同時に申請したい」というケースに強く、最短での免許取得に向けた段取りを一緒に考えることを大切にしています。
第5章|申請に必要な書類一覧
個人と法人で変わる添付書類の注意点
宅建業免許申請では、「こんなに出すの!?」と思うほど多くの添付書類が必要です。
申請者の属性(法人か個人か)によって異なる部分も多いため、正確に準備しておかないと差戻しになる可能性も。
この章では、石川県での申請における主要書類と、その取得ポイントをまとめます。
■ 共通で必要な書類(法人・個人共通)
| 書類名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請書一式 | 免許申請書、誓約書、略歴書など | 石川県書式に準拠 |
| 事務所の使用権原を証する書面 | 賃貸契約書、登記簿謄本など | 自宅の場合も必須 |
| 事務所の平面図・周辺案内図 | 間取り図・地図 | 専用スペースが明確であること |
| 宅地建物取引士証の写し | 専任宅建士の証明書 | 有効期限の確認を |
| 身分証明書・登記されていないことの証明書 | 役員・専任宅建士分 | 法務局と本籍地の市区町村から取得 |
| 納税証明書 | 直近分(法人税・住民税) | 未納がないことを証明するため |
| 営業保証金・弁済業務保証金の準備書類 | 宅建協会の加入申請書など | 協会に加入する場合は別途書類が必要 |
■ 法人申請で追加される書類
| 書類名 | 説明 |
|---|---|
| 履歴事項全部証明書(登記簿謄本) | 設立から3ヶ月以内のもの/法人情報 |
| 定款の写し | 法人の目的に「宅地建物取引業」が含まれていること |
| 役員全員の略歴書 | 欠格事由の確認目的で必要/全員分提出 |
特に注意したいのが「目的に宅地建物取引業が含まれていない」ケースです。
この場合、定款の変更登記が必要になり、1〜2週間以上のロスが生じます。
申請前にしっかり確認しておきましょう。
■ 個人事業主で必要な書類
| 書類名 | 説明 |
|---|---|
| 住民票 | 本人の住民票/マイナンバー記載なしのもの |
| 所得税の納税証明書 | 所轄税務署から取得/過去の納税実績を確認する目的 |
| 個人事業の開業届 | 提出済であれば写し/ない場合でも相談可 |
個人事業主の場合、「これから始める予定」という方も多いため、実績がなくても取得自体は可能です。
ただし、営業の実態や誠実性を示す補足資料が求められるケースもあるため、事前相談が非常に重要です。
■ 書類取得の際の注意点
- 発行日が古いと差し戻される
⇒ 通常は3ヶ月以内、ものによっては1ヶ月以内が目安 - 本籍地や法人の所在地により、平日しか取得できない書類も多い
⇒ 事前にスケジュールと窓口をチェック!
■ 当事務所では、全ての書類取得をサポート可能!
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 書類収集の代行
✅ 本籍地や法務局への郵送取得サポート
✅ 定款修正の手続き調整(司法書士との連携)
✅ 書類の順番・ホチキス留めなど提出直前の仕上げまで
を一括して対応。
「自分でやったけど戻された…」というお悩みも多いため、最初からプロに任せるのが結果的に早いというケースが増えています。
第5章|申請に必要な書類一覧
個人と法人で変わる添付書類の注意点
宅建業免許申請では、「こんなに出すの!?」と思うほど多くの添付書類が必要です。
申請者の属性(法人か個人か)によって異なる部分も多いため、正確に準備しておかないと差戻しになる可能性も。
この章では、石川県での申請における主要書類と、その取得ポイントをまとめます。
■ 共通で必要な書類(法人・個人共通)
| 書類名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請書一式 | 免許申請書、誓約書、略歴書など | 石川県書式に準拠 |
| 事務所の使用権原を証する書面 | 賃貸契約書、登記簿謄本など | 自宅の場合も必須 |
| 事務所の平面図・周辺案内図 | 間取り図・地図 | 専用スペースが明確であること |
| 宅地建物取引士証の写し | 専任宅建士の証明書 | 有効期限の確認を |
| 身分証明書・登記されていないことの証明書 | 役員・専任宅建士分 | 法務局と本籍地の市区町村から取得 |
| 納税証明書 | 直近分(法人税・住民税) | 未納がないことを証明するため |
| 営業保証金・弁済業務保証金の準備書類 | 宅建協会の加入申請書など | 協会に加入する場合は別途書類が必要 |
■ 法人申請で追加される書類
| 書類名 | 説明 |
|---|---|
| 履歴事項全部証明書(登記簿謄本) | 設立から3ヶ月以内のもの/法人情報 |
| 定款の写し | 法人の目的に「宅地建物取引業」が含まれていること |
| 役員全員の略歴書 | 欠格事由の確認目的で必要/全員分提出 |
特に注意したいのが「目的に宅地建物取引業が含まれていない」ケースです。
この場合、定款の変更登記が必要になり、1〜2週間以上のロスが生じます。
申請前にしっかり確認しておきましょう。
■ 個人事業主で必要な書類
| 書類名 | 説明 |
|---|---|
| 住民票 | 本人の住民票/マイナンバー記載なしのもの |
| 所得税の納税証明書 | 所轄税務署から取得/過去の納税実績を確認する目的 |
| 個人事業の開業届 | 提出済であれば写し/ない場合でも相談可 |
個人事業主の場合、「これから始める予定」という方も多いため、実績がなくても取得自体は可能です。
ただし、営業の実態や誠実性を示す補足資料が求められるケースもあるため、事前相談が非常に重要です。
■ 書類取得の際の注意点
- 発行日が古いと差し戻される
⇒ 通常は3ヶ月以内、ものによっては1ヶ月以内が目安 - 本籍地や法人の所在地により、平日しか取得できない書類も多い
⇒ 事前にスケジュールと窓口をチェック!
■ 当事務所では、全ての書類取得をサポート可能!
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 書類収集の代行
✅ 本籍地や法務局への郵送取得サポート
✅ 定款修正の手続き調整(司法書士との連携)
✅ 書類の順番・ホチキス留めなど提出直前の仕上げまで
を一括して対応。
「自分でやったけど戻された…」というお悩みも多いため、最初からプロに任せるのが結果的に早いというケースが増えています。
第7章|石川県での申請サポート実例
地域密着の行政書士が選ばれる理由とは?
宅建業免許の申請は「全国一律のルール」に基づいているようで、実は自治体ごとに運用や審査の姿勢が微妙に異なります。
ここでは、石川県における特徴や、行政書士高見裕樹事務所が実際に対応した事例を通じて、地域密着の強みをご紹介します。
■ 石川県の免許申請は「県庁 」で
石川県内の宅建業免許申請では、事務所所在地により提出先が異なります。
| 所在地 | 提出先 |
|---|---|
| 金沢市・小松市・白山市など | 石川県庁土木部建築住宅課 |
| それ以外の地域(七尾市、かほく市など) | 石川県庁土木部建築住宅課 |
この違いにより、「書式」「添付資料の指示」「受付対応」などが若干異なります。
たとえば、白山市では写真の貼付け位置にまで細かい指定があるケースも。
地域の慣例を熟知していないと、形式的な不備で足止めをくらうこともあるため、地元の実情に通じた行政書士のサポートが非常に有効です。
■ 実例①:用途地域の確認で“足踏み”したケース
小松市での法人申請において、事務所が店舗併用住宅の一部にあり、
用途地域が「第一種低層住居専用地域」に該当していたため、
宅建業の事務所として認められるか不明確という事態が発生。
【当事務所の対応】
✅ 都市計画図と用途地域図を取り寄せ
✅ 建築士に依頼して用途確認と事務所仕様の図面を整備
✅ 市の建築課・宅建窓口の両方と協議を行い、「営業実態あり」として通過
用途地域は「申請書には出てこない盲点」ですが、現地での判断が左右する要素です。
行政書士が前面に立つことで、こうした“灰色ゾーン”もクリアに導きます。
■ 実例②:宅建協会加入をスムーズに進めた事例
金沢市の法人様が宅建業免許取得後、石川県宅地建物取引業協会(いわゆる「宅建協会」)への加入を希望。
しかし協会側からは以下の書類準備と面談調整が求められ、営業開始が遅れる懸念が生じました。
【当事務所の対応】
✅ 加入申請に必要な書類をすべて事前に準備
✅ 納入金額の試算とスケジュール表を作成
✅ 協会との連絡調整・日程確保を代行
✅ 加入後の標識・帳簿類まで準備し、営業開始をスムーズに
「免許が出てもすぐ営業できない」状況を避けるには、協会との連携がカギです。
当事務所は協会対応にも慣れており、スムーズな開業をバックアップできます。
■ 実例③:個人事業主の申請で「実績がない」不安を解消
能美市で宅建業を始めたいという個人のお客様。
ただし過去に宅建業経験がなく、「申請しても不許可にならないか不安」とのご相談。
【当事務所の対応】
✅ 事業計画書と収支予測書を作成
✅ 開業予定物件の写真とレイアウトを提示
✅ 専任宅建士との雇用契約書を添付し、「運営体制が整っている」ことをアピール
結果、追加質問もなく、スムーズに免許が下りました。
「これからやる人」でも、しっかり準備を整えれば許可は取れます。
■ 地元密着の強み:すぐ現地に駆けつけられる
宅建業免許の申請では、
- 物件の写真を再撮影
- 図面の追記・差替え
- 市役所との打ち合わせ同行
といった「現地対応」が必要になることがあります。
石川県に拠点を置く行政書士高見裕樹事務所なら、現場への即対応が可能。
他県の事務所では対応が難しい部分までフォローできるのが、大きな強みです。
第8章|宅建業免許申請はプロに任せるのが正解な理由
「自分でできる」と「確実に通る」は違う
宅建業免許の申請は、行政庁のHPを見れば、
✅ 申請書類の一覧
✅ 記載例
✅ 提出方法
が掲載されており、「自分で申請できる」と思われがちです。
しかし、実務の現場では以下のようなトラブルが頻発しています。
■ ありがちな“自力申請”の落とし穴
- 不備があって何度も通うことに…
→ 書類は一式揃えても、「記載内容に矛盾がある」と差戻し - 担当窓口が常に同じとは限らない
→ 窓口によって見解が違い、求められる添付資料もブレる - 協会加入の準備が間に合わず営業できない
→ 免許は出ても、開業が1〜2ヶ月遅れる事態に - 「開業日」に間に合わず賃料や人件費だけが先行
→ 余計なコストがかさむ
つまり、「書類を出せば通る」は大きな誤解です。
■ プロに依頼することで得られる“5つの安心”
当事務所の宅建業免許申請サポートは、単なる「書類作成代行」ではありません。
| 安心のポイント | 内容 |
|---|---|
| ① 不備のない書類作成 | 条件に合った書類の準備からチェックまで一貫対応 |
| ② スケジュール管理 | 希望開業日に間に合うよう逆算して手続き設計 |
| ③ 行政との事前協議 | 用途地域・独立性・専任性など微妙なケースも事前に折衝 |
| ④ 宅建協会加入の支援 | 協会書類の準備・面談日程調整・費用案内などもカバー |
| ⑤ 不測の事態にも対応 | 写真の撮り直し/補正依頼/急な面談への同行も可能 |
特に石川県内では、「役所ごとの判断基準」や「書類の細かいクセ」を熟知していなければ、たとえ正しい内容でも“形式不備”として受け付けてもらえないリスクがあります。
■ 実績ある事務所だからできる「開業までのトータルサポート」
行政書士高見裕樹事務所では、
- 物件選びの段階から用途地域をチェック
- 許可取得後の協会加入・営業開始届まで対応
- 不動産会社として宅建業の実務にも精通
しており、「とりあえず免許を取る」だけで終わらせません。
また、ふちどり不動産・Kプランニング(内装施工)との連携により、物件紹介・内装工事・ホームページ作成まで一貫支援も可能。
まさに「宅建業開業のワンストップ支援」を実現しています。
▼まとめ:宅建業免許は、スタートラインに立つための第一歩
宅建業免許を取得することは、あくまでも「事業のスタート地点」に過ぎません。
その後、営業開始・顧客獲得・業績拡大と進めていくには、開業時の準備段階でどれだけ“段取り良く”進められるかが鍵になります。
「いつか宅建業をやってみたい」
「今の仕事の幅を広げたい」
「不動産事業を法人化してしっかり収益化したい」
そんな想いがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの不動産ビジネスのスタートを、全力でサポートいたします。
📩 お問い合わせはこちら
行政書士高見裕樹事務所では、宅建業免許申請に関する無料相談を受け付けております。
以下のフォームより、お気軽にお問い合わせください。
👉 行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム
「https://takami-office.net/contact/」